LOCAL LETTER


クリエイティブがまちを変える。分野や地域の「越境」が生み出すものとは
ZENKOKU
全国
拝啓、クリエイティブでまちが変わるって、どういうこと?と感じているアナタへ
※本レポートは、株式会社WHEREと東海旅客鉄道株式会社が主催する「地域経済サミットSHARE by WHERE in 東海」のNAGOYA CONNÉCT コラボセッション「まちづくりクリエイティブ論。クリエイターが生み出す、まちの変容とは!?」を前後編で記事にしています。
地域をフィールドに、新たなまちづくりにクリエイティブな側面から取り組む4名による今回のトークセッション。
前編では、「クリエイターの定義」や「専門領域を超えた仕事の在り方」について、登壇者それぞれの活動をふまえてお話いただきました。
>前編はこちら<
後編では、「地域にない仕事を生み出す」ことや「他の地域への横展開」に関する議論をお届けします。

クリエイターの存在が、移住やUターンのきっかけに
水谷氏(モデレーター、 / 以下、敬称略):前半では「まちの変化」についても少し触れましたが、クリエイターもしくはクリエイティブがまちに変化を及ぼした事例はありますか?

今尾氏(以下敬称略):ヒダカラさんをみて、同じまちなのに1つの会社が入ることで「こんなにも変わるんだ」と思います。ふるさと納税を軸に、デザイナーと一緒に次々と新しい商品を生み出していて、すごいなと。創業6年目にして、人口約2万2000人の飛騨市にいまや45名もの従業員を抱えているヒダカラさんは存在感がありますね。


水谷:人口を考えると、なかなかの存在感ですね。
舩坂氏(以下敬称略): 若くて優秀な人たちが楽しく働いて、地元に帰るきっかけができたと思ってもらえるようになったのは嬉しいですね。移住やUターンで「働き先がやっと見つかった」と転職してくださる方も多いんです。

水谷:もともと地元に帰りたかったのに、自分を受け入れてくれる会社や楽しいと思える仕事がなかったという観点からも、ヒダカラさんのニーズがありそうですね。
舩坂: 地域には企画系の仕事が不足しているので、そこをカバーできているのも大きいですね。
勝亦氏(以下敬称略):昨年、ARCADE HOTEL(アーケードホテル)を開業した時のことを思い出しました。うちは勝亦丸山建築計画と富士山まちづくりという2つの会社を経営していますが、設計事務所の求人は本当に難しくて。求人を出してもなかなか応募が来ない。インターンの応募はたまにあっても、その後、定着しにくい。

勝亦:だから地域での求人は難しいんだろうと思っていたのですが、ARCADE HOTELの開業後、アルバイトの募集をしたら、応募がバンバン来るんです。例えば、海外から帰ってきた20代の子。
地元の富士市で数年間の羽休めができるような場所を探していたけれど、希望する仕事が全然なかった、と。ヒダカラさんと似たような動機の応募が多数あり、地域にはこんな市場があったんだと改めて感じました。

水谷:多拠点生活などの移動型とはまた違う、1箇所で落ち着いた暮らしを求める人たちの受け皿でもあり、企業観が変わるお話ですね。そう考えると、移住者誘致よりも先に、まちへの企業誘致を頑張るべきなのではとも感じます。
「あの人に頼めばなんとかしてくれる」が、新たなきっかけ
勝亦:先ほど、今尾さんの周りには、いろんな分野の仕事を複合的に取り組むデザイナーが多いという話がありましたが、僕の周りにはあまりいなくて。専門領域をはみ出していかない人が多いんです。だから今尾さんのお話を聞いて、特殊だなと感じました。
今尾: そうですね。僕らは商店街でお店を始めて、そこからデザインの仕事が増えていった流れがあるので、僕らがやっているデザインは、世間で言われるデザインから少し離れているのかもしれません。広義の意味でのデザインで、仕事の範囲はとても広いですね。
水谷:広義と狭義のデザインがあるなかで、デザインを広義で捉える人が今尾さんの周りには多いという印象ですね。

今尾:はい。地域では、守備範囲が広くないと逆に仕事にならなかったりもします。だから、うちはデザイン以外にも、編集もやったり。必要と思われる仕事は比較的なんでもやります。
舩坂:今尾さんのところに頼めば「なんとかしてくれるに違いない」と、今までやったことのない仕事をよく頼まれたりしませんか?
今尾:はい、まさに。
舩坂:そこが越境ポイントなのかと思います。飛騨市には、企画や人材募集などソフトの困り事を相談できる会社が少ないため、私たちの会社でも同じようなケースがあります。これまでに経験のない依頼でも、クリエイティビティのひとつとして壁をひとつ超えてみる。その積み重ねなのかな、と。

勝亦:たしかに、客観的に自分たちが「守備範囲が広い」「この範囲までできる」と周囲に認知されているかどうかによって、越境が成功したか判断できそうですね。
水谷:そうですね。例えば、僕らの会社、On-Coは「何やってるのかわからない」とよく言われます。僕らは仕事の場所を地域を限定していないし、街中にある会社なのにニワトリも飼っていたりして。なぜかというと、新しいことを試さないと、僕たちは新しさを失うんじゃないかという恐怖心があるんですよね。
もうひとつの理由は、地域に入ることへの躊躇。ひとつの地域を背負うことに、「そんなたいそうなことをしていいのか」という一種のためらいがあります。だからひとつのまちに限定して、まちごと変容させる、というアプローチはしたことがないんです。
地域を限定するか、広げるか。クリエイターとまちの関わり方
水谷:地域との関わり方について、みなさんの場合はどうですか?
勝亦:僕の場合はUターンで、富士市に戻ってから、その後、関わるまちが増えています。関わり方は様々あるものの最初はケーススタディといいますか、実験的なフィールドとして捉えています。
富士市で起きた自分の展開や成り行きのなかで、「何が再現性があるのだろう?」とか「どの市場や場所なら再現できるのだろう?」といつも考えていて。どこでも再現できるわけではないと思うのですが、これまでの実験で得たナレッジが、どこか他のまちとうまくマッチングすれば、それらを応用できる気がしています。

水谷:「まちの事例の横展開」と呼ばれる話だと思うのですが、横展開について、他の方はどう思われますか?
舩坂: 横展開ができないことがあるのも、地域の面白さでもありますね。
例えば、Webマーケティングなら色々と横展開できるはず。ですが、地域においては、本質的には横展開できないことも多くて、増産するのも難しいと思うこともあります。 でも、そこをいかに乗り越えるかと考えるのが、私たちの役目なのかもしれません。
水谷:例えば、前半で話にあがった、ふるさと納税の「おっちゃんレンタル」の話。単純に、おっちゃんが増えたら、売れたらいいのかという話になると、どこかで純粋なおっちゃんではない人が現れてきそうな気がします。これらのさじ加減って、ものすごい難しいなと思って。
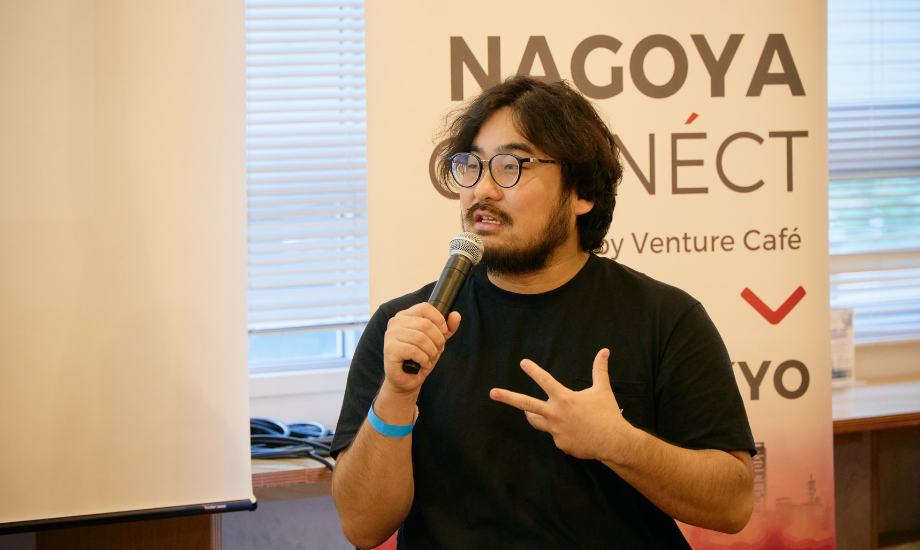
勝亦:なるほど。ただ、カタチのあるプロダクトとカタチのない哲学的なものや、スキル・知見などはまた違うと思っていて。こうした無形のものをまちに持ち込んでどう変化していくか、ということが横展開だと僕は思っていて、そのままスライドするのとは違うようにも感じますね。
今尾:僕らは岐阜での仕事が多いのですが、ひとつの仕事を終えたら、そこからの紹介で次の仕事が来るという流れを繰り返していたらこうなったというだけであって。だから、地域の制限をかけているわけではなく、結果的に岐阜のデザイン会社という認識になったと感じています。
だから、東京でも愛知でも、声がかかれば地域を越えて仕事をします。
ですが、自分たちが頑張ってデザインしたものが近くにあるというのも大きい。例えば、地域のお店を新たにデザインさせてもらうと、完成後もお店に行けるし、社内のメンバーも「その場」を楽しめる。僕らと一緒に働いてくれている人たちにも楽しんでもらいたいな、と考えると活動エリアが狭くなりがちで、横展開しにくい気がしてしまいますね。
専門領域のその先へ。クリエイターが越境するために必要なこと
水谷:僕らは、不動産を借りたい人と大家さんとのマッチングサービス「さかさま不動産」を展開しています。とある古民家サウナができるまでの出来事を紹介させてください。

水谷:一般的に、古民家をサウナとして使わせてくれるところはなかなかない。ですが、古民家の大家さんと一緒にサウナに行ったりして人としての関係性を深めたら、結果的に大家さんが僕らに借主の人選を委ねてくれたんです。結局、人と人との関係性があればうまくいく。
今尾:属人的でもありますし、「そこに熱量があるかどうか」という点も大事ですね。冒頭に「クリエイターとは?」という問いがありましたが、「熱量を持った人」も付け加えたいですね。
まちで頑張っていると「いつも頑張っているから」という視点で、新しい仕事という形で僕たちに投資をしてくださる方もいます。僕らもフェーズが変わってきて、若い人たちに仕事をお願いする立場になった時、「できるから」というより「この人ならやってくれそうだから」という気持ちで依頼することもあります。
勝亦:大家さんにせよ、発注者にせよ、類似実績がない人に仕事を発注するのは少し不安じゃないですか。それを「熱量や属人性でカバーできることが多い」という話だと思うのですが、発注者の不安な気持ちをどうしたら依頼したい気持ちに転換できるのでしょう?

今尾:もちろん類似実績がある会社の方が、タスクとしての仕事はできるとは思うんです。今日の会場である「なごのキャンパス」で例えるなら、この空間を作ったら終わりなのか、その後、この空間に熱量を持たせて「ここから新しいものをどんどん生み出す」という場所としての機能まで担うのか。どこまでを仕事の範囲として捉えているかによると思います。
今尾:地域では、空間を作ったものの、うまく活用されないことも多くて。そう考えると、熱量がある人がその空間にいないと、場所としての機能が維持できない。だから熱量のある人に仕事を頼みたいという側面はあると思います。
水谷:僕らも似たようなケースがありました。3000人規模の会社の理念を一緒に作って欲しいと依頼があったのですが、実は、僕らもやったことがない分野。
でも発注のきっかけは、僕らの熱意を知ってもらったことだったんですね。こんな面白そうな仕事なら「絶対にやってみたい」と思った、その熱量が大事だったろうなと思います。

今尾:いろいろな仕事に携わるなかで、結局、熱量があるものが最終的にうまくいくと感じています。実績のありなしに関わらず。
水谷:そういう意味では、まちの変容というのは、まち側が選ばなければいけないのだから、熱量を持った人にスポットライトを当ててみるのは必要かもしれないですね。それが、飛騨市のおっちゃんかもしれないし、フェスやイベントで盛り上がった空き家の話かもしれない。その熱量を「このまちでちゃんと実践させよう」という姿勢も大きいのかもしれないですね。
クリエイターにまちを変容させてもらうんじゃなくて、変容を起こしたいクリエイターたちを、まちが主体的に選べるか?という視点で。
舩坂: そうですね。あとは純粋な熱量に加えて、会社を存続させるために「絶対やらなきゃダメ」という必死感。どちらもクリエイターとしての成長に効くんじゃないかと思います。
一同:それは本当にそう思います。
舩坂:きっと、クリエイターなら誰しもが大なり小なり経験したことがあるのではないでしょうか。
それぞれのまち、それぞれのクリエイター論
勝亦:期待値が高くて遠いものをまちに呼び込み何かを仕掛けていくよりは、今あるリソースを見直して、それらをフル活用して、どうやってまちに落とし込むかと考えた方が、最終的にちゃんと回るんじゃないかなと。発注する側もクリエイター側も。
そんなサイクルがまちの色々なところで起きてくると、まちが変容していくのではないかと思います。
今尾:まちって、チームプレーだと思うんですね。色々な役割の人がいて、その中にクリエイターもいて。
駆け出しの頃は、名刺デザインの仕事で5000円いただくところから始まって、なんとか食べつないで…というフェーズもあったと思うんです。それをひとつひとつ頑張って、徐々に仕事が増えていく。
ここで、まちをチームとして考えると、チームが今後このまちをどう育てていきたいか、つまり投資していきたいかという視点になるとも思うんです。まちの若手に新しい仕事を任せれば、「まちがチームメンバーを育てている」ということにつながると思うんですね。

今尾:発注する側もクリエイター側も、目先の仕事だけに終わらない、一歩先の未来に対して投資する姿勢も大事かなと。
舩坂:今日の登壇を通じて、クリエイティブとかクリエイターが関わる領域には大きさが色々あるんだなと思いました。
「まちの未来をこうしたい」という視点もあれば、「明日の自分をこうしよう」という視点もあって、どれもクリエイティブ。こうしたさまざまなクリエイティブができる人が、まずは沢山いることが、まちにとってすごくいいんだろうなと思います。
とはいえ、まちづくりって、すごく難しくて。今尾さんがおっしゃったように、お願いしたり、お願いされたりという流れがあって。お願いされる側が「作る人 = クリエイター」というだけでなく、お願いする側のクリエイティブも大事だな、と今日は何度も思いました。

水谷:今回のようなトークセッションですと、つい結論を出したくなるものですが、皆、背景も活動領域も違うから、あえてひとつにまとめる必要もないのかな、と。
「まちの変容」は熱量だけでは簡単に解決できるものでもないから、みんな悩んでいるわけであって、簡単な答えはない。ですが、登壇者の皆さんそれぞれの経験ややり方を通じて、新たなヒントやきっかけが見えてきて、参考になる部分は多いなと思いました。
そして、僕もみなさんのまちに遊びに行ってみたいと思いましたし、聴講された皆さんの中にも、そう感じた方が多いのではないでしょうか。実際に現地に足を運び、今日のような話を共有していくことが、遠回りに見えて一番の近道なのかもしれません。
今日はありがとうございました。
Editor's Note
編集後記
人としての熱量、今あるリソース、そして未来への投資。時にはいろいろな制約もありつつも、いまはまだ形になっていないものを「どう創造していくか」を考えることが、地域におけるクリエイティブなのではないかと感じました。

NATSUKO
夏子
Articles
