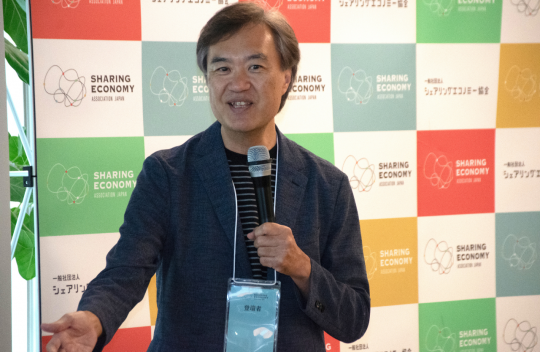LOCAL LETTER
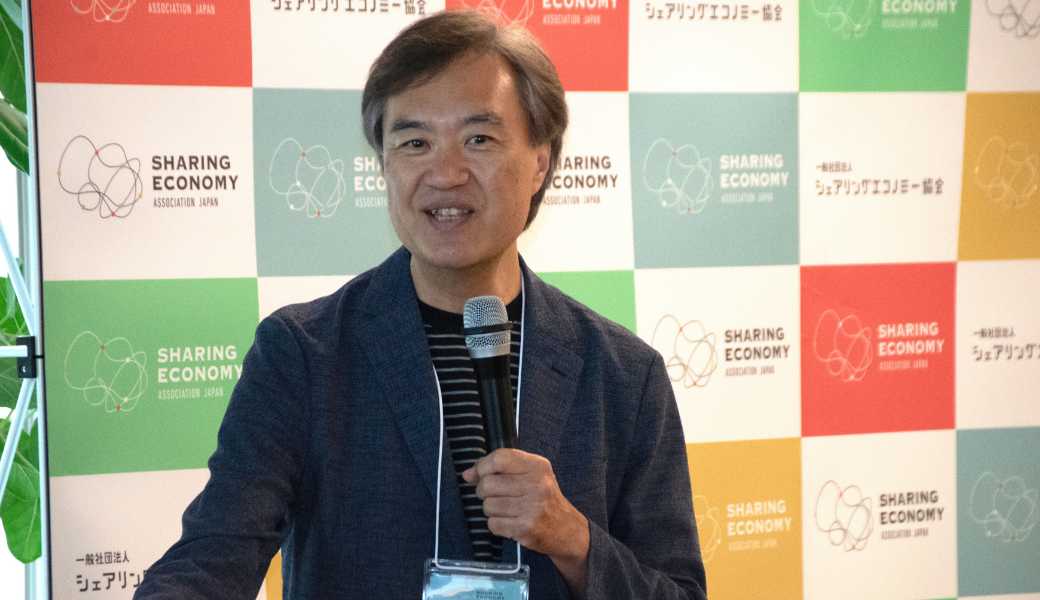
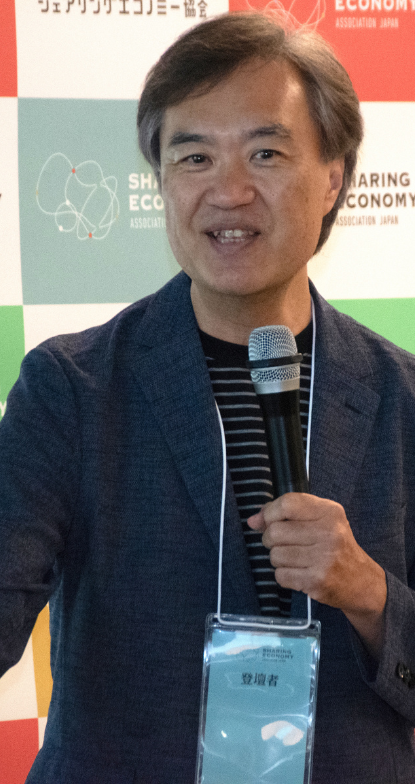
第2のふるさとが身近な時代へ。広がり続ける関係人口と、二地域居住の進化
ZENKOKU
全国
拝啓、二地域居住を迎えるまちづくりに、一歩踏み出したいアナタへ
※本レポートは、『シェアリングフォーラム2025』のSession3『関係人口&二地域居住×シェア「地域内外の人をつなぎ未来に続くまちをつくる〜ひとや地域をつなぐシェアの活用〜」』を前後編で記事にしています。
関係人口や二地域居住は、静かなブームから“実践”の段階へと進みつつあります。
前編では、大手企業・自治体・スタートアップそれぞれの立場から、関係人口と地域をつなぐ最前線の実践が語られました。
後編では、それらの実践の中で見えてきた変化や課題、そして“これから”の関係人口・二地域居住のあり方について、さらに深く掘り下げたトークセッションが繰り広げられました。

>前編はこちらから<
理想から実現へ。人と地域をつなぐ仕掛けが生んだ、関係人口と二地域居住の変化
津田氏(以下敬称略):最近皆さんが感じている、“関係人口”や“二地域居住”の変化やトレンドについてお伺いします。この言葉自体は以前からよく使われていますが、最近変わってきた実感はありませんか?
まず大屋さんにお聞きしたいのですが、個人的にもとても興味があるのが、ホストの存在です。ゲストを関係人口へとつなげていく過程において、ホストは非常に大きな役割と感じています。その辺りも含めてお話いただけますか?

大屋氏(以下敬称略):私がAirbnb Japanに入社したのは2016年ですが、その頃から宿泊施設のホストがゲストと地域をつなぐことで、二地域居住の促進や関係人口の増加に寄与すると言っていました。それは今も変わりません。ただ、当時はまだ「こういったことを目指しましょう」という段階でした。
それがここ2〜3年で、リアルに実行する人が増えたと感じています。「こんな場所にも宿があるんだ」と驚くような地域にも、不動産をリノベーションした宿が増えている印象です。
空き家を購入して、“半分暮らす”というライフスタイルを希望する人も増えています。日本だけでなく海外からも「どうすれば購入できるのか」といった問い合わせが、ものすごく増えています。
もちろん、住民感情などに配慮する必要はありますが、語るだけではなかなか広がりません。実際に暮らし始めるきっかけを作り出せているのが、ここ数年の大きな変化だなと感じています。

津田:そういったゲストの方々に、どうすればホストになってもらえるんでしょうか?
大屋:最近は“民泊インフルエンサー”がずいぶん増えてきています。「こうやって始めるとうまくいくよ」など、自分のノウハウをコミュニティでシェアしてくれるのが大きいですね。“商売”に特化した方もいれば、ゆっくり始めたい方など、色んなタイプの方がいます。
そういったインフルエンサーの方を大切にしながら、口コミ+αの力で、ホストになってくれる方を増やしています。
また、最近は自治体とのパートナーシップにも取り組んでいます。地域の方々が半信半疑だと定着しないし、理解が進まないので、旗振り役となってくれる自治体のパワーはすごいです。
津田:続いて菅野さんにもお伺いします。プレゼンのグラフデータで気になったのですが、「西川町ファン」がめちゃくちゃ増えていますよね?!どんな仕掛けをすると、こんなに増えるのでしょうか。
菅野氏(以下、敬称略):最初のきっかけは、今までリーチしなかった若い世代の観光客に来てほしいと思ったことです。まちの強みを活かしながら、この地域には1つもなかったサウナを作りました。補助金は5年間ですが、サウナ自体はその後もずっと使うことができます。

津田:それにしても、西川町ファンが急増していますよね。
菅野:役場の“つなぐ課”の職員が、丁寧に人と人をつないでいるんです。なるべく地域の人と交流してもらって、関係人口を増やしています。最初は職員がお手本となりますが、自然と地域の方がホスト役になっていって、どんどんつながるようになりました。
津田:“つなぐ課”についても、詳しくお伺いしたいです。
菅野:やっぱり自治体も、関係人口の価値を理解しないと、政策が立てられないんです。予算を通すにも、議会に説明できないといけない。私はたまたま現場経験があってうまくいきましたが、経験がないと難しいと思うんです。
“つなぐ課”では、「来る人も迎える人も、両方が笑顔になること」をモットーとして学んでもらっています。わざわざつなぎ役がいるのは手間でもあるのですが、実際にやってみると、やっぱりその方がよいと周りが感じることもわかりました。
地域指導者となる中間管理組織がないのが、日本の地方全体の課題だと思います。まちの観光協会から独立して地域商社を立ち上げた方もいますが、やっぱりやってみてわかったということでしょうね。
そうして地域にお金が循環する仕組みとなり、だんだん理想的な形に近づいています。
津田:そういった「動ける人」を見つけるのも、難しいことだと思うのですが……。
菅野:見つけるというよりは、育てていくことが大切だと感じています。
津田:続いて、西村さんにお聞きします。先ほど、世界中に支援者の方がいて、地域と交流されているとお話されていました。どのように関係人口につなげているのか、改めてお伺いしたいです。

西村氏(以下敬称略):やはり、リターンを得るだけではなく、「投資を通じて学びを得たい」という方が多いです。なので、地域と関わるモチベーションも非常に高いのだと思います。
先ほど菅野さんからも“民泊インフルエンサー”のお話がありましたが、一時「日本の不動産がお得」という内容の投稿がバズったんです。ニューヨークタイムズに取り上げられたこともありました。それが世界中で知られるきっかけになったと感じています。
そうして日本の地方物件に興味を持つ人が増えたのですが、実際に所有して管理するのはなかなか大変です。そのため、“共同所有”という形で、いろんな地域を訪れて学びたいという人が増えています。
一方で地域側からすると、短期ステイになってしまうのは避けたいです。そこで、ワーケーションを取り入れたり、地域の魅力を知ってもらうために仕事を手伝ってもらっています。そうしたことが話題になって広がっているのだと思います。
津田:投資家がどんどん地域に行って、地域も活性化して、楽しい取り組みですね。そもそも物件がないとできないことですが、物件探しのコツがあれば教えていただけますか?あるいは難しさとか。
西村:そうですね。重要文化財など、価値が高い物件は難しいです。そして「この物件を残したい」という想いを持っている人がいないと、成立しません。
我々も全国にチームがあるわけではないので、現状は人とのつながりでご紹介いただいている状態です。描いたロードマップ通りに進めるのはなかなか難しいと感じています。ただ、ありがたいことに投資は集まっている状態なので、物件さえご紹介いただければぜひ地域に伺います。
関係人口と二地域居住のさらなる推進のために。当事者が感じる“制度”の課題
津田:今日は政府や自治体、事業者の方々も多く参加されています。今後の推進に向けて感じている課題や、「こうしてほしい」と思う要望があれば、皆さんにお聞きしていきたいと思います。
まずは大屋さんにお伺いします。旅館業は規則とのバランスも難しいと思うのですが、その辺りも含めていかがですか。

大屋:まさに、民泊をやろうとすると、旅館業法・住宅宿泊事業法・国際戦略特区の取り組みに該当します。もちろん法が整備されているのは良いことです。しかし、プロセスが複雑だったり、所管官庁がバラバラだったり、いざ「はじめよう!」とした時にくじけやすいのが課題です。
さらに、地域ごとに簡単に理解するには複雑な“ローカルルール”もたくさんあります。消防等はその典型として、解釈に難しさがあるといわれている領域で、地域毎に明文化されていないような運用があることも多いです。安全のための規則はもちろん大切ですが、わかりやすく平準化させることが重要なポイントだと思います。
津田:続いて菅野さんにお伺いします。関係人口の話になると、地域住民の目線も重要ですよね。場合によっては住民の税金から補助金が出ていることもあると思います。住民側の気持ちで、難しいこともあるのではないでしょうか。

菅野:そうですね。例えば地方では、町内会費を払っていないとゴミが捨てられないといったローカルルールもあります。
こういったローカルルールを、二地域居住者が増えてきたときに、自治体が見直す必要があると思います。別荘地など、そういったことに慣れている地域もありますが、そうではない地域は、1〜2ヶ月に1回だけ来る人を想定してルールができていないんです。
私は3年前まで国にいた立場なので感じますが、“二地域居住法”を作ってメリットをしっかり自治体に伝える必要があると思います。どのようなルールが必要で、導入コストがどのくらいかかり、どのようなメリットがあるのか。そういったことをしっかり情報開示して進めて欲しいと思います。
津田:西村さんは、特に金融商品や伝統的建造物を扱う中での難しさはありますか?

西村:大屋さんもお話されていましたが、消防法のように整備が必要なルールはたくさんあると思います。特に私たちが扱っている重要文化財のような建物だと、明確なルールがオンラインに掲載されていないことも多いです。各市区町村に確認をとったり、複数の段階を踏む必要があります。課題というよりは、ステップとして見ているところですね。
また、私たちは株式で運営しているので、例えば市の方々に「この株を持ってくれませんか?」とお願いしても、難しいと言われることがあります。今後、市や自治体とも一緒にプロジェクトを進めたい想いがあるので、一緒にできる方法を模索していきたいと考えています。
地域と人のつながりを広げ続けるために。関係人口と二地域居住の次なる実装
津田:最後に、この『シェアリングフォーラム』を中心に、今後の関係人口や二地域居住の取り組みに対する想いや展望を、一言ずついただければと思います。

大屋:先ほども申し上げましたが、ようやく実需が見えてきました。協会の皆さんが頑張ってきた成果で、これからは実需を確実なものにしていくフェーズに入っていくのだと感じています。
「うちのまちには名物がない」とおっしゃる方も多いのですが、そんなことはありません。どこもしっかりとした魅力的な場所だという実感を持っていただきたいです。本当にやれるんですよ、皆さん!我々もしっかり全国津々浦々にお伺いして、それを伝える活動をよりがんばっていきたいと思います。
菅野:私は国家公務員のときに、10年間“地方創生”に携わってきました。これからは、二拠点居住で人を増やすことを、アクティブに進める自治体を作っていきたいです。
また、先ほど西村さんのお話にもあったように、ソーシャルインパクトボンドのような仕組みを通じて、空き家の改修や移住促進に民間投資を呼び込めるスキームづくりもしていきたいと考えています。
現在はタイミーさんと組んで、人が移住したら投資家にリワードが発生する配当制度を作っているところです。自治体だけでなく、民間と連携することも、金融商品には重要だと思います。
西村:投資家の方々にとっても、物件のオーナーにとっても、「1人で所有するよりも共同所有が安心」といった話をよく聞きます。また、実際に宿泊施設として運営を始めてからも、冬はやりづらいなど地域の季節ごとの特性や、雇用の難しさがあります。
シェアリングエコノミーが地域にどんどん普及することで、私たちもプロジェクトが展開しやすくなると感じています。

津田:ANAでは乗り降りの際に、もう20年以上もの間、流している曲があります。葉加瀬太郎さん作曲の『アナザースカイ』です。和訳すると、『第2のふるさと』ですね。どちらが拠点ということではなく、みんなが行ったり来たりして欲しいという想いからこの曲を流しています。
関係人口や二地域居住の人たちが、地域を行き来する時代はすでに始まっています。どんどん増えていけば、交通事業者だけでなく、さまざまなシェアリングエコノミーの事業者、その利用者、みんながつながり、地域が活性化していくと思います。
Editor's Note
編集後記
“移住”は少しハードルが高くても、「ちょっとだけ地域に関わってみたい」「第2のふるさとを持ってみたい」。そんな想いを、あたたかく迎えてくれる地域の存在が、こんなにも広がっていることに驚きました。
地域側も「どう受け入れるか」「どう関わってもらうか」を丁寧に考え、仕組みを整えてきたことが、今日の広がりにつながっているのだと思いました。
関係人口や二地域居住は、もう特別な誰かの話ではありません。これからの地域と私たちを、もっと自由につなげてくれるように感じました。

MIO
mio
Articles