LOCAL LETTER


空っぽになった自分から始まる。ご縁を紡いで築く、まちづくりのキャリア
ZENKOKU
全国
拝啓、自分の生き方に確信を持って地域と関わりたいアナタへ
アナタは今、自分のキャリアに確信を持てているでしょうか?
「このままでいいのかな」「本当にやりたいことって何だろう」——そんな迷いを抱えながら、日々を過ごしている人も少なくないはずです。
今回お話を伺ったのは、飛騨信用組合で電子地域通貨「さるぼぼコイン」を生み出した、古里圭史さんです。公認会計士の資格を取得後、東京の大手監査法人で実績を積みました。現在は慶應義塾大学大学院の特任准教授や株式会社リトルパークの代表取締役など、複数の肩書きを持つ「まちづくりプロデューサー」として注目を集めています。
誰もが羨む華々しいキャリアに思えますが、その裏には多くの挫折と苦労がありました。
「自分が空っぽになってしまった」と語るほどの苦しい状況から、いかにして今のキャリアを築き上げていったのか。その歩みは、生き方に迷う多くの人にとって、確かな指針となるのではないでしょうか。
計画的ではない、けれど確信に満ちたキャリアの築き方。そして地域と真摯に向き合う古里さんの姿勢から、これからの時代を生きるヒントを探ってみました。
挫折の先に見つけた、新しいキャリアの築き方
「正直、計画的なキャリアというものは全くありませんでした。その時々のご縁と目の前にあることに従って動いた結果、気づいたら今のキャリアになっていたんです」

現在は金融のプロとして全国の地域に関わる古里さんですが、学生時代は全く違う道を描いていました。
高校時代は医師を目指して医学部受験に挑戦するも思うような結果を得られず。大学時代にはプロのミュージシャンを志し、事務所から声がかかることもありましたが、最終的にはその道も断念。二つの大きな夢が立て続けに崩れ去った時、古里さんの心は深い喪失感に包まれました。
「連続で挫折して進路からこぼれ落ちた時に、自分が何者なのか分からなくなって、何をしたらよいのか全く見えなくなってしまったんです」
明確な目標を持ち、そこに向かって突き進むキャリア設計。古里さんがそれまで当たり前だと思っていた生き方が根底から崩れた瞬間でした。しかし、この挫折こそが古里さんのキャリア観を根本から変える転機となりました。
「大きな目標を描くやり方では自分はうまくいかないとわかり、それからはわらしべ長者のように、目の前のことに集中して取り組むようになりました。その結果、今やるべきものが見えるようになって、さまざまなご縁がつながっていったんです」
大きな目標を掲げて突き進むのではなく、目の前にあることに誠実に向き合い、出会いを大切にしながら一歩ずつ歩んでいく。古里さんはそんなアプローチを選択するようになったのです。
計画がなくても道は見える。今を積み重ねて育った”確信”
古里さんのキャリアは、従来の大きな目標を設定してそこに向かって突き進む「トップダウン型」ではなく、目の前の機会を大切にしながら経験を積み重ねていく形で築き上げていかれました。
計画に縛られず動くことは、一見リスクにも思えます。それでも古里さんは、流れに身を任せながらも自分なりの軸を持ち、考え続けてきました。そのバランスをどのように保ってきたのでしょうか。
「自分がやっていることを、後からでも『ひとつのストーリー』として説明できるようにしていました。取り組んでいるときは意味が分からなくても、『なぜこれをやっているのか』を考え続ける。
そうやって自分の中で意味づけを積み重ねていくことが、大切だと思っていました」
そうすることで、一見バラバラに見える経験が一本の線としてつながり、自分のキャリアに一貫性と納得感が生まれていきました。
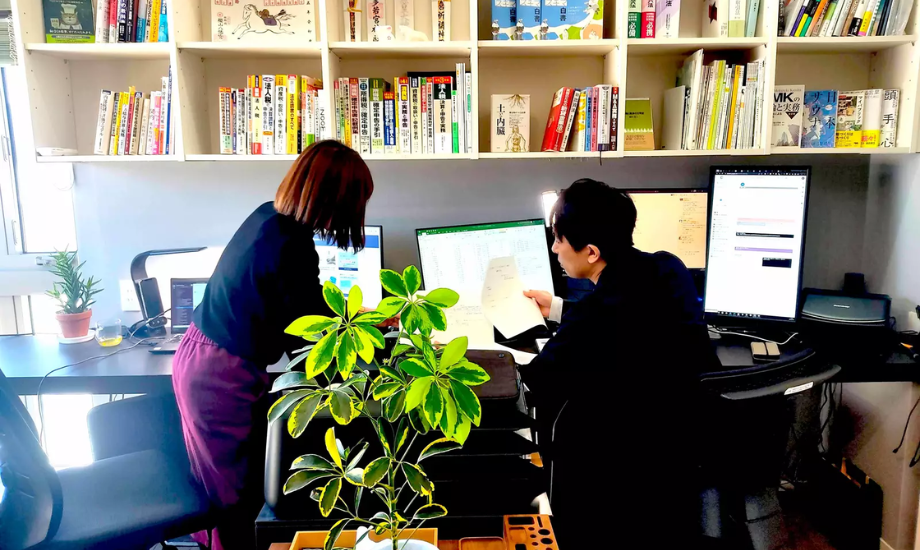
「あとは、目の前のミッションをすべて確実に果たすことだけに集中してきました。そうすると『今何をやっているんだろう』という不安を感じることがあまりありません。
その時は意味が分からなくても、自分の中にある『種』のようなものが芽吹いて育てば、今やっていることが間違いなく資産になる。それが次につながるのだという直感はずっと持っています」
現在進行形の取り組みに対する「確信力」。これこそが、古里さんのキャリア構築の核心部分なのかもしれません。
寄り添い、ときに立ち向かう。 飛騨で見つけた「中庸」の距離感
目の前のご縁を大切にしながらキャリアを積み上げてきた古里さん。公認会計士として東京の大手監査法人で経験を積んだのち、2012年10月、地元の飛騨高山へUターンしました。地域に根ざしたコミュニティバンク「飛騨信用組合」に入組し、そこで新たな挑戦が始まります。しかし、いざ地元の飛騨に戻った時、想像していなかった大きな壁が立ちはだかりました。
「高校まで育った場所だったので、自分が知っている世界とそれほど違いがあるとは思わずに戻ってきてしまったんです。でも実際は、語り口や人との接し方、コミュニケーションの仕方など、自分の振る舞いを相当変えないといけないと痛感しました。
地域では、職場の上司が実は親戚の知り合いだったり、取引先の社長が同級生の親だったり、一人の人に対して、『上司』『地域の先輩』『知人の家族』といった複数の関係性が同時に存在する難しさがあります」
仕事上の役割だけで完結しない、何重にも絡み合った人間関係。地域という場所の特性のひとつです。この複雑な関係性をどう乗り越えるかが、古里さんにとって大きな課題となりました。
「難しさに気づいてからは、自分の論理を押し付けないことを徹底しました。共感力を働かせて、丁寧にコミュニケーションに気を遣うこと。それは今でも変わらず続けています」

「あとは、地域の側に寄り添う立ち位置は大切にしつつも、地域の外側にいるアドバイザーの立場として冷静に意見を伝えることも意識しています。いわゆる『中庸』のあり方を強く意識するようにしているんです」
「中庸(ちゅうよう)」とは、物事に対して極端に偏らず、過不足なく調和が取れていることを指す言葉です。古里さんの場合、それは変化を押し付けるのではなく、まず寄り添うこと。そして寄り添うだけではなく、必要な変化も促していくというバランス感覚を意味しているようです。
「郷に入っては郷に従えの考え方を大切にする一方で、プロジェクトの進め方や考え方でよくないことは、はっきり『ノー』と伝えるようにしています。何かをやる際の目的と結果に対しては強くこだわって、ときには真っ向から意見を交わすこともあります」
寄り添うべきところは寄り添い、厳しく指摘すべきところは遠慮なく指摘する。その絶妙なバランス感覚こそが、古里さんの「中庸」のあり方です。
「支援」ではなく「伴走」。挫折が教えてくれた人との向き合い方
古里さんを語る上で欠かせないもう一つの特徴的なスタンス、それは「支援」ではなく「伴走」する姿勢です。
「一方的に、『こうして欲しい』とお願いしたり指示したりすることがあまり好きではなくて。むしろ、『一緒にやろう』という形で関わることに、少しこだわりがあるんです」
支援という言葉には、どうしても「支援する側」と「支援を受ける側」という上下関係のニュアンスが含まれてしまいます。古里さんが違和感を抱くのは、まさにそういった一方向性の関係性です。
代わりに古里さんが大切にしているのは、自分もプレイヤーとして地域に関わる対等な立場での「伴走」という考え方です。
「もちろん外部の立場からアドバイスすることもありますが、それだけでは地域を変える効果はそれほどない。口を出すなら、同じだけ手も動かそうよって思うんです」

「中庸」や「伴走」の言葉に込められた、古里さんの人との向き合い方。その背景には、冒頭でも述べたキャリアの原点となる挫折の経験がありました。
「悩んでもがいていた時期に、建築現場で働くなどさまざまな肉体労働を経験しました。そこで出会ったのは、それまでの自分の世界では接点のなかった、本当に多様な層の方たちでした。
一直線に医師やミュージシャンを目指していた頃の自分は、成功への最短ルートだけを見ていたと思います。でも脱線したことで、いろいろな生き方、いろいろな価値観を持つ人たちと触れ合うことができた。その経験が、自分の考え方の思考回路を根本から変えたと思います。
もしあのまま順調にキャリアを積んでいたら、人の気持ちを理解するとか寄り添うということが、今のようにはできていないと思います」
「好き」の感情を胸に地域に飛び込んでほしい
古里さんの独自のスタイルは、確かに多くの成果を生み出してきました。しかし、古里さん自身が強調するのは、自分のやり方が唯一の正解ではないという点です。
「相手に寄り添ったスタンスを取ると、なかにはもっとガツンとやって欲しいといった声もいただきます。つまり、地域づくりに『これが正解』という単一の答えはないんです。
地域にはいろいろなスタイルの人がいて、だからこそうまく機能するんだと思う。ガツンと言う人もいて、僕みたいな関わりをするタイプの人もいる。そういう多様性があってこそ、地域に意味のある施策ができるんだと思います」
古里さんは「地域の関わり方も一つではない」と続けます。語る姿からは、自分の立ち位置から関わり方を模索する人たちへの温かなまなざしが伝わってきました。
では、これから地域と関わってみたい人は、何から始めればよいのでしょうか。古里さんのアドバイスは明快です。
「好きな『地域』と『人』を見つけるのがすごく大事なんじゃないかな。特定の地域に継続的に関わる際、いいこともあればすごく厳しい、辛いこともいっぱいあります。だからこそ、困難な時期を乗り越えるための動機が必要です。
そこで、『こういう仕事をしたい』とか、『こういう人が好き』だからここにいるんだという、エモーショナルな動機がすごく大切だと思います」
そして古里さんは、最初から深く関わろうと気負う必要はないとも語ります。
「今はいろいろな関わり方ができると思うんです。お試しで、月に1回は定点観測的に通うとか、自治体がやっている移住のお試し制度を使って関わりを持ち始めてみるとか。
ライトなものからでもアクションを起こしてみると、違う世界が広がるはずです。
最初はどんな形であれ、関わっていけば『自分はなぜこの地域に関わりたいのか』『どんなことができるのか』が少しずつ見えていきます。その理由が自分の中で腑に落ちてしまえば、きっと次の一歩は自然に見えてきます」

古里さん自身のキャリアがそうであったように、最初は小さなご縁から始まって、気がつけば大きな流れになっている——そんな自然な展開こそが、最も持続可能な地域との関わり方なのかもしれません。
アナタには、心が動く地域がありますか?一緒に何かをやってみたいと思える人がいますか?
もしそんな感情があるなら、それこそが地域との関わりを始める最初の一歩になる。古里さんの生き方が教えてくれるのは、そんなシンプルで力強いメッセージなのです。
Editor's Note
編集後記
古里さんのユニークで人をひきつける生き方が生まれた背景には、簡単に言葉にすることが難しいような葛藤がたくさんあったのだと思います。でも、その葛藤一つひとつと丁寧に向き合い、今目の前を確かに生きる力に変えていった誠実な姿勢に、困難に立ち向かう勇気をもらえたような気持ちになりました。

Yusuke Kako
加古 雄介
Articles
