LOCAL LETTER

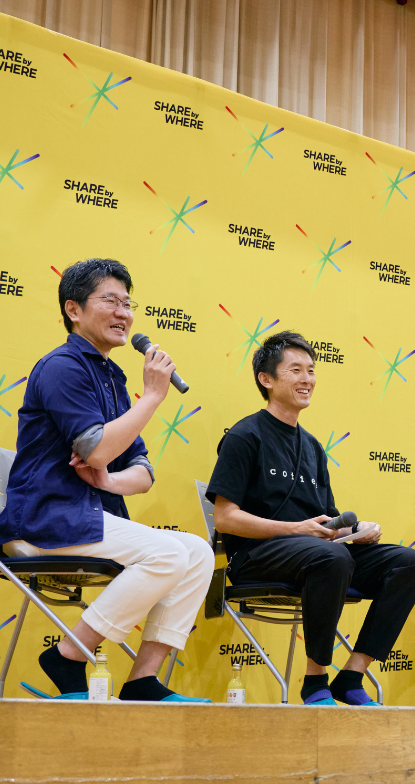
小さな発見が、まちの風景を大きく変える。暮らしを起点に育てる不動産開発
ZENKOKU
全国
拝啓、眠っている不動産で、暮らしに変化をもたらしたいアナタへ
※本レポートは、株式会社WHEREが主催するトークセッション『地域経済サミットSHARE by WHERE in 東海』のSession3「売買だけじゃなく育てる不動産開発とは?」を前後編で記事にしています。
まちの風景や空気感は、身近な小さなきっかけから変わっていく。
そこに暮らす人々のライフスタイルの変化や想いに合わせて、不動産を“育てて”いきませんか。
今回のトークセッションには、地域で実践を続ける4人のプレイヤーが登壇。本記事では、それぞれの取り組みやまちへの向き合い方から、「暮らし」を起点にまちが変わっていくプロセスをご紹介します。

地域に根ざす4人のプレイヤーが語る。暮らしを軸にした不動産開発の最前線

矢ヶ部氏(モデレーター / 以下、敬称略):まずは、1人ずつ自己紹介をしていきましょう。私は公共R不動産の矢ヶ部と申します。社名に「不動産」とついていますが、いわゆる不動産業ではなく、行政などが使わなくなった学校や廃校などの施設を、新たな形で活用する取り組みをしています。
こうした事例は近年増えており、今後さらに広がっていくだろうと感じています。私たちは、それらの事例を紹介したり、「どうすればもっと上手くいくのか」といった視点で、不動産のより良い活用方法を研究したりプロデュースしたりしています。
もともとは再開発事業のコンサルティングを20年ほどしていて、その後「まちをガラッと変える」というような不動産開発の現場にも携わるようになりました。通算で約30年間、不動産関連事業に関わっています。
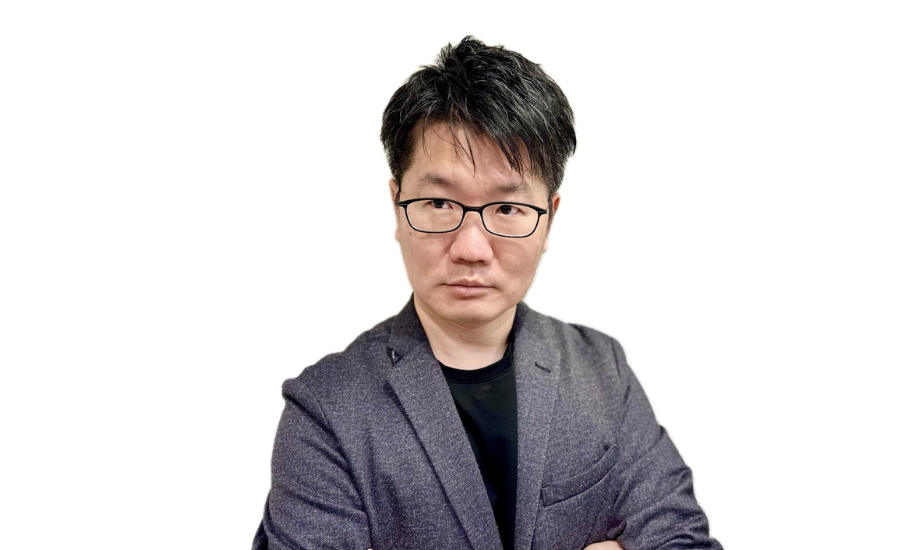
中川氏(以下、敬称略):岡崎市役所のまちづくり推進課で、中心部でウォーカブルなまちを目指す都市戦略「QURUWA(くるわ)戦略」を推進して13年目になります。
出身は三重県伊勢市で、大学で名古屋に来て、そのまま岡崎に来ました。今は市役所職員として、多様でおもしろい民間や市民の方と関わることができています。すごく楽しい仕事をさせてもらっていて、公私を横断してまちに携わっています。

中川:QURUWA戦略というのは、ちょっと変わった名前ですが、岡崎のまちなかにある公共空間を舞台にした公民連携プロジェクトです。観光というよりも「暮らしの質を上げること」をベースにしていて、その先に観光があるという考え方で進めています。
私は立ち上げ当初から関わっていて、QURUWAの営業担当のような存在だと思っています。今日はこの中で唯一の公務員です。岡崎市役所職員として、公共空間を周辺の民間空間とセットでどう活用していくかをプロモーションしている立場として参加しています。
矢ヶ部:公務員とはいえ、地区で一番大きい不動産オーナー企業の社員みたいですよね。 実は私もQURUWAの取り組みには少し関わりがあるのですが、そんなお話も後ほど伺えればと思います。
瀬川氏(以下、敬称略):Studio Tokyo Westの瀬川と申します。空間デザインやパッケージデザインなどを手がける会社ですが、不動産オーナーでもあります。東京の吉祥寺でシェアハウスを2つ運営しており、片方は私も住んでいる“ファミリーで暮らすシェアハウス”です。

瀬川:シェアハウスを基軸に、入居者たちと近隣に食堂やお惣菜屋さん、ワークショップスペース、バーを展開しています。まちのプレイヤーと連携しての事業も行っています。
特定のエリアにこだわり、集中して事業を展開してきました。今では7つの事業があり、すべて自転車で回れる範囲です。
10年以上やっていると、まちの風景もかなり変わってきました。不動産とプレイヤーの協働が、まちにどのようなパワーを与えるのか、そんなお話ができたらと思います。

矢ヶ部:自分たちが欲しい物は自分で作っていくスタイルですね。しかもそれが事業とは、なんて幸せな!なぜそのようなことができるのかも、後ほど掘り下げていきたいと思います。では続いて、小口さんお願いします。
小口氏(以下、敬称略):岐阜県多治見市から来ました、小口と申します。観光協会のCOOという、少し不思議な肩書きで活動しています。
多治見市の観光協会は、まちづくりに取り組む会社2社と観光協会が合併して、3年前にできた組織です。商店街の活性化や空き不動産の活用、直営の飲食店の運営、リノベーション、ゆるキャラのお世話など、様々なことをやるところです。

小口:不動産に関しては、賃貸物件や空き店舗をリノベーションして自分たちで事業を始めたり、駐車場を保有したり、行政と連携しながら運用したりしています。そうして得た収益を、観光やまちづくりに活かすということを、繰り返し続けてきました。
どちらかというと、観光だけじゃなく日々のまちづくりが好きな観光協会だと思っていただけたらと思います。
必要なものは、自分たちで作る。高校生が相続した、空き家から始まるまちづくり
矢ヶ部:今日の登壇者に共通しているのは、まちに対して、暮らしづくりにフォーカスした関わり方をしている点だと思いました。
ここからは、行政との関わりについて伺っていきます。瀬川さんは民間、中川さんは行政、小口さんは行政と民間の中間、こうした立ち位置ですかね。
まずは瀬川さんに、民間の立場でどのようなことをやっているのか、また困っていることなどがあれば、教えていただけると嬉しいです。そもそも、瀬川さんは、どのような経緯で事業を始めたのですか?
瀬川:そもそも事業を始めたのは、相続がきっかけなんです。まだ高校2年生のときで、ボロボロの古い物件でした。

矢ヶ部:会場からも驚きの声が!高校2年生で相続せざるを得なかったのでしょうか。どうしようって感じですよね。
瀬川:そうなんですよ。ちょうど進路を考える時期とも重なっていて。そんな時にたまたまコンビニで、リノベーションの特集を見かけました。
ちょうど当時、“リノベーション”という言葉が出始めたくらいの頃で、「こんなにボロボロの物件が、かっこよくなるんだ!」と興味を持ちました。インテリアや内装も面白そうだなと思って、建築学科に進むことにしたんです。
矢ヶ部:えーっ!相続がきっかけで、そこから進路を決めたんですか?
瀬川:そうなんです。「建築家になるぞ!」と意気込んだんですけど、当時の建築の世界って茨の道で過酷な修行のイメージもあって。
なので、女性が今の時代にあった働き方で建築家になるにはどうしたらいいかを考えていました。そこで「この物件を使って、自分らしい事業を始めるのはどうかな」と思い至って。大学2年のときに、シェアハウスをつくりました。
学生同士で始めたので、最初は大学生が集まって暮らしている感じでした。

瀬川:そこから年を重ねて、結婚したり、子どもが生まれたり、独立して設計の仕事を始めたり。そういう入居者の変化に合わせて、必要な設備も変わっていきました。
子育てできる環境とか、広めのキッチンとか、子どもをみながら働ける場所も必要。他にも、ごはんを毎日つくるのが大変だからお惣菜屋さんも作っちゃえ、みたいな感じで。
結婚式をするときも、吉祥寺にいい式場がなかったので、素敵なお花屋さんや美容院やドレス屋さんと一緒に、吉祥寺のお気に入りの場所で式をあげられる仕組みを作っちゃいました。
身近な仲間を主人公に。目の前のニーズが次の世代のまちへつながる
中川:私は行政で建築の方とやりとりすることがあるんですけど、設計して作るまでは出来ても、その後の運営までできる人は少ないと思っています。瀬川さんはその辺りはナチュラルに進められたのでしょうか。
瀬川:私は運営が先だったんです。運営しながら学生として勉強もしていく中で、どういうデザインだったら、自分たちがやっていることをかっこよく、刺さる人に刺さるべく届けられるだろうという風に、デザインの方に力を注いできました。

中川:一般にクライアントワークから入るところを、日常から入るのは面白いですね。
矢ヶ部:たくさんの事業を、すべてお一人で回しているわけではないと思うのですが、ほかにはどんな方々と一緒に活動されているんですか?
瀬川:そうですね、全然一人ではできなくて。むしろ設計以外は、会社が母体ではありますが、わりと各部署に任せている事業が多いです。
たとえば飲食店の店長は妹ですし、10年ぐらい一緒に暮らしている子にウェディング部の部長として式の事業をお願いしたり。とにかく、身近にいる人を“主人公”と見立ててプレイヤーにしちゃうような手法をとってきました。「まちに投入していく!」みたいな感じです(笑)
小口:お話を聞きながら、うちも観光協会とはいえ、“まちづくり会社”のDNAが強いと改めて思いました。私が最初の社員として入り、今はスタッフが50人ほどいて、店長をしたり、まちづくりのキーパーソンのような立場で自主的に動いてくれています。
結局、自分たちの「欲しい」をどう実現していくかを考えながら動いているところが大きくて。今のお話を聞いて、羨ましく思いながらも、似ているようにも感じました。
瀬川:そうそう、「やりたい」を全力でサポートするのが、ゼロイチの立ち上げでは一番スピード感がありますよね。
小口:そうでないと、作ったはいいけど続かないものになってしまいますよね。ライフステージに合わせて住み方や、やることを変えていくというお話も、理想的だなぁと思いました。

瀬川:マーケットリサーチにこだわるよりも、目の前の人や身近な人のニーズに丁寧に応えていく感覚でやってきました。身近な誰かをペルソナにすると、その人たちが引っ越した後でも、似たようなニーズがそのまちにあることが、今まで多かったと思います。
中川:「土地があるけどどうしよう」といった相談を周りから受けることもありますか?
瀬川:そうですね。「不動産をどう使うか」というよりは、「こういうことやってみたい」という相談が多いかもしれません。
たとえば、「本屋を始めたいんですけど」とか。それで一緒に物件を探して、「どんな本屋にする?」と話したり。
中川:そっちの方が、まちにとっても良い流れですね!
行政と協働して、暮らす人が“面白い”と思うまちへ
矢ヶ部:小口さんの“まちづくり会社”は、どんな風に始まって、今はどんな状況なのでしょうか。
小口:大学で長野県から金沢市に来たのですが、商店街の皆さんが、アルバイト先でイベントの打ち上げをしていたんです。それがきっかけで、“まちづくり”という仕事があることを知りました。

小口:多治見市でもまちづくりの会社を再生したいという話があり、移住してまちづくりを担うことになったんです。それまで社員が1人もいなかったところに、はじめての社員として迎えていただきました。
最初は実質的に動かしているのは行政の方々だったため、まちの人からも「行政の人でしょ」と認識されたり、色々厳しいことを言われたりしてしまって。
「まちの課題を解決しながら、仕事をしているまちづくり会社なんだ」という姿を見せたくて、カフェを始めました。なんというか…お客さんを迎える気がない、まちづくりでありがちなカフェにはしたくなくて。
瀬川:「まちづくりでありがちなカフェ」って、ちょっとダサいってことですよね?(会場笑)
小口:そうならないように意識しながら作りました。幸い、行列ができる話題のカフェとなって、名古屋の情報誌にも取り上げてもらえました。
そこから地域の皆さんに「こういうことができるんだ」と知っていただけましたし、まちの人や行政の方々も協力してくださって。そんな形で仕事が増えていきました。

矢ヶ部:どうしてカフェだったんですか?
小口:当時リーマンショックの後で、人件費は県の委託事業として出すから、地域の失業者を雇って、地域のために事業を作りましょうという緊急雇用があったんです。
私自身、実家が飲食店だったり、調理師免許を持っていたりしたので、飲食なら自分で運営しやすいと思いました。あとは、商店街に女性客を含め、多様な来客を増やしたかったというのも理由です。
瀬川:カフェをはじめた頃、周りはどういう状況だったんですか?
小口:商店街は店舗が減るばかりで、新しく出店されるというのは、聞いたことがないような状況でした。
ただ、まちに残っている人たちは、「楽しくしていきたい」という想いを持っていて、自分たちで手作りのイベントをやるような空気感でした。僕らが何かはじめると、みんなでペンキ塗りをしたり、応援してくれました。
中川:観光協会というと行政と一緒に進められているイメージもありますが、実際の財源はどうなっているんですか?

小口:今は年間で2億5千万円くらいの売上で、そのうち9千万円は駅近くの市営駐車場の運営収入です。あとは行政から受託している観光マーケティングが5千万円くらい。その他に、飲食・物販・リノベなど、直営事業からの収入もあります。
矢ヶ部:不動産は、持っていないんですか?
小口:今は持っていないのですが、まさに購入を検討中です。
賃貸だと「返して」と言われたりテナントが抜けたりしたときに負担が大きいので、自由に使える拠点を持ちたいと思っています。まちの人たちと一緒に動いたり、まちに来て欲しいプレイヤーの方々もいるので、そういう人たちの取り組みの場を作りたいんです。
矢ヶ部:今は、どんな方々が活動されているんですか?
小口:正規職員は10人ほどです。飲食や駐車場、案内所、広場の運営などのスタッフを合わせると、50人くらいです。移住してきた人やUターンの人もいて、「地元で仕事したい」「多治見が面白そう」と言って入ってくれる人もいます。
矢ヶ部:暮らしてる人たち自身が、「面白いと思える」って、非常に良い状態ですよね。
小口:そうなんです。だから会社としても、そういう働き方ができるように柔軟に変えてきました。就業規則も、どんどんアップデートしているところです。
瀬川:観光地って、暮らしの満足度が分かれますよね。地域のためにやっていることが結果的に観光にもつながっているケースと、とにかく外貨を稼ごうとしすぎて、地域の満足度が下がってしまっているケースも…。
矢ヶ部:ちょうどそういったお話しも伺いたいと思っていました!中川さんから、岡崎市のQURUWA戦略についても聞かせていただけますか?
風景と共に変わった、まちの空気。信頼される行政の“関わり方”とは

中川:私は大学卒業後すぐ市役所に入って、今23年目で、土木職なんです。最初の10年は、道路や河川、水道工事の工事発注や現場監理など、まさに“ザ・土木”の仕事をしていました。
当時は苦情も多くて、正直、全然幸せじゃなかったんですよね…。でもまちづくりの仕事を始めてからは、一気に仲間が増えて超ハッピーです。
工事担当していた時は、民間の方とは契約関係しかなかったのですが、契約のないフラットに関わる関係がどんどん広がって、QOLがめちゃくちゃ上がったんです。プライベートでもまちに関わるようになって、すごく幸せだなと思っています。
まちづくりは13年目ですが、最初の5年は本当に大変でした。市長の「乙川(おとがわ)を生かしたまちづくりを推進する」という公約のもと、年数千万円規模の業務を地元のまちづくり系NPOに委託して、双方過酷な状態で働いていました。夜中の1時とか2時とか、電源が落ちるまで市役所にいることがけっこうありました。
それが変わったきっかけは、2019年に完成した籠田公園(かごだこうえん)のリニューアルです。元々は近隣住民さえ誰も訪れないような、7,000㎡ほどの小さな公園でした。リニューアルされて、まちのイメージというか、空気感が本当に変わって。誰も否定できない風景ができたんですよね。

中川:当時、まちのご意見番のおじいちゃんたちの一人が、「これが市のやりたかったことか。ようやく理解できた。後は任せた」と言ってくれたんです。そこからどんどん、前向きに話が進んでいく流れが出来ていきました。
エリア内に6年連続で18店舗ほど出店が続いて、徐々に地価が上昇したり、市民税や固定資産税も上がっていたりするような状況になってきています。QURUWA戦略の完成には肌感覚としてまだまだ20〜30年かかりそうですが、引き続き関わっていきたいと思っています。
矢ヶ部:ご意見番が「わかった」って言ってくれるの、涙出そうですね…!
仕事として行政に関わっているのと、中川さん“個人”として関わっている感覚とで、変化ってありましたか?
中川:そうですね。民間の方の多くは、行政という組織との付き合いではなく、「行政の○○さん」のような固有名詞と付き合っていると思うので、それに応えられるようにしたいと思っています。
民間の方が一番嫌がる“はしご外し”は避けられるよう、極力担当者が変わらないようにしたり、日々声を挙げながら頑張っています。
矢ヶ部:このセッションのテーマにも“育てる”とありますが、小さなことから始めたり、最初はなかったところに実績を作ったら共感が生まれたり、という話が皆さんから出てきましたね。
そして、そこに関わっている人たちは「自分たちの欲しいものを作っている」というのがモチベーションなのだと伝わってきました。ただ、そもそもなぜそこへ巻き込まれたのかという、“巻き込まれ方”にも特徴があるのではないかと思っています。
民間だと「自分たちの間でやればいい」という動き方もあるけれど、どうしても行政からの関与も多くなりますよね。“まちづくり”という言い方になった瞬間に、しがらみや、動きづらさも出てくるのではないかと。
今回の“育てる不動産”というテーマにおいて、行政のスタンスとか、どんな距離感がよいのかというのも、けっこうポイントになる気がしています。そのあたり、中川さんどう思いますか?

中川:行政としてまず大事なのは、民間の方々の“邪魔をしない”ことだと思います。実際にまちづくりをする民間の方々をリスペクトして、行政の役割(例:規制緩和、制度づくり、地域との調整等)が必要なときは、ちゃんと登場する。
その行政の役割が必要で、さらに他部署を巻き込む必要があるときに、民間の言葉を行政向けにパブリックな言葉に翻訳して「公共性があって、すごくまちのことを思っていて…」と、民間を応援できるプレゼンを市役所内でやっています。
できる限り早くスピード感をもって調整して、動かせるよう努力しています。
矢ヶ部:裏を返すと、行政が邪魔をしがちってことですか?
中川:そうなんです。行政側から民間に提案するパターンもあって、やらせた後は継続しなくて、民間が困ることもよくあります。企画がずれているというパターンもありますね。やはり民間が責任をもって進めることができるように、企画から運営まで民間が責任をもって進めることができるような事業でなければやるべきではないと思います。
矢ヶ部:“邪魔をしない”って、すごく大事なキーワードですね。「行政」「民間企業」「地域」の三角形がどんな形が一番いいか、行政が環境整備してくれるのが理想ですよね。
Editor's Note
編集後記
まちの風景が変わるきっかけは、日々の小さな想いや行動でした。身近な人の暮らしを想う気持ちから、次の世代につながる不動産が育っていく。その積み重ねが、未来のまちを作っているのだと感じました。

MIO
mio
Articles
