LOCAL LETTER


人生ゲームを武器に。公務員×NPO代表として実践した越境のまちづくり論
SHIMANE
島根
拝啓、 「やりたい」はあるけど「無理はしたくない」アナタへ
公務員として、そしてNPOの代表として。二つの立場を行き来しながら、地域に関わり続けてきた人がいます。その人の名は、島根県出雲市役所職員・田中寛さん。
田中さんが手がける『まちあそび人生ゲーム』は、商店街を舞台にした体験型イベント。参加者は実際に店を訪れ、商店主とやり取りしながら「人生」を進めていきます。
公認を得たタカラトミー社の「人生ゲーム」の世界観と、地元のリアルが交差する仕掛けは、子どもから大人までを惹きつけ、地域活性の新しい形として注目を集めてきました。
この取り組みは2013年、出雲市の小さな商店街からスタート。以来10年以上にわたり、その活動は山形・静岡・愛知など、全国へと広がり始めています。
やりたいことを、やめないために。無理をしないまちづくりを10年続けてきた人がいます。
商店街の“違和感”から、リアル人生ゲームの種が生まれた
島根県出雲市で公務員として働く田中さんが最初に感じたのは、「イベントって、本当に商店街のためになっているのだろうか?」という素朴な疑問でした。
商店街の賑わいを演出するために開催されるイベント。しかしその実態は地元の店舗が売上に結びつくこともなく、店を閉めて裏方として奔走する場面も少なくありません。
現場でそうした声を耳にするうちに、田中さんの中に「何かがおかしい」という思いが芽生えました。
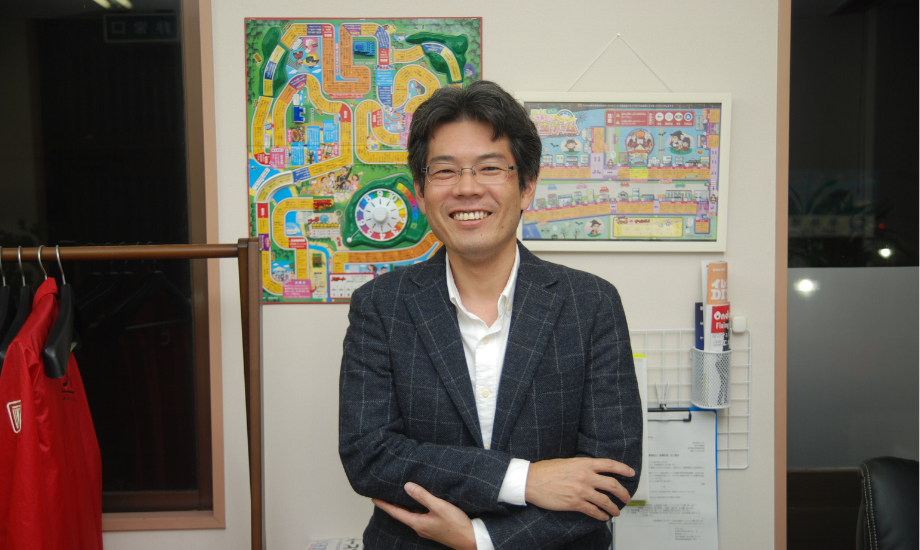
「夏祭りやイベントは、たしかにお客さんは来るけど、商店街の人は店を閉めて、裏方でただ疲れて終わっている。それは本当に商店街振興なのか?と思ったんです。結局、そのたこ焼きやかき氷といった露店はにぎわっても、お店の商品が売れるわけじゃない。
商店街の人たちが駐車場の案内をしたり、チケットを売ったりして、儲かりもしないし疲労だけが残る。そんな話をよく聞いていました」(田中さん)
そんなある日、きっかけは飲み会の雑談から突然訪れます。
それはアーケード商店街にある居酒屋での会話でした。参加者は市の職員から民間企業の人まで幅広く、世代もバラバラ。意外な話題が共通点となりました。

「アーケードの店の並びが上から見ると人生ゲームのマス目に似ているよね、という話で盛り上がったんです。そこにいたのは、ちょうど当時30代後半の自分を中心に、上は50代、下は20代という構成でした。
『今どきの若い子は何して遊んでるの?』と聞いたら、『人生ゲームです』って返ってきて。人生ゲームはその場にいた全員が知っていた。そこから『リアル人生ゲームを商店街でやったら面白くない?』っていう話になったんです」(田中さん)
問題意識から生まれた違和感と、何気ない会話から湧き上がった遊び心。それが、のちに10年続く『まちあそび人生ゲーム』と呼ばれるプロジェクトの原点になりました。
広げようとしないから広がった、10年続く取り組みの理由

『まちあそび人生ゲーム』は、出雲市の平田本町商店街で2013年にスタートし、初回の参加者は406人。それが年々増え、2016年には2,500人以上が参加する一大イベントへと成長しました。
商店街復興のモデルケースとして、手応えを感じていた田中さん。しかし、実際には最初の数年は思うように広がらなかったといいます。
「最初の3年くらいは、まったく広がらなかったんですよ。イベントの話をしても『よくわからない』と断られることが多くて。でも僕ら(当時3人の中心メンバーで進めていた)のスタンスとして、『イベントを実施してください』と営業する気はなかったんです」(田中さん)
この時期、全国の商店街関係者に向けて、活動をアピールする機会もあったといいます。しかし、すぐに『まちあそび人生ゲーム』実施につながるケースはそう多くはありませんでした。
それでも田中さんたちは、無理に広げようとはせず、「必要とされる場所で、自然に根づいていくこと」のほうが大切だと考えていました。

「地域振興の押し売りみたいにはしたくなくて、面白そうと思って声をかけてくれたら全力で応える。でも、こちらから売り込むのは違うというのが、運営メンバー3人で共有していた感覚でした。
まちゼミや100円商店街といった、当時すでに全国で地域おこしの活動を展開してる人たちと出会い、『まちあそび人生ゲーム』と紹介してもらうなかで、ようやく少しずつ実施につながっていきました」(田中さん)
活動を続けるうえで大切にしてきたのは、無理をせず、必要とされるときにこそ全力を尽くすこと。
そして立ち上げの頃から一貫していたのが、「頑張りすぎない」というスタンスでした。
「メンバー3人で話し合い、“無理はしない”ということは最初に決めていました。それぞれ本業をしっかり持っていて、メンバーの一人は会社経営者で僕は公務員。本業も大事にしたい。だから、“オファーが来すぎたら断ろう、無理に広げすぎない”と、初めから確認していました」(田中さん)
頑張らないからこそ、続けられる。地域と無理なくつながる関係性が、この10年の歩みを支えてきたのです。

公務員として、NPOとして——2つの肩書きを行き来して
公務員という立場を持ちながら、NPOの代表としてもまちづくりに関わっている田中さん。行政か民間かどちらかだけに属するのではなく、田中さんはその“あいだ”を自由に行き来してきました。
公務員とNPO活動が相互に作用し合い、今ではもう「どちらも本業」という感覚なのだといいます。
「NPO活動を通じてつながった縁が、公務員の仕事にも自然と生きてきたんです。なので副業というより、むしろ本業の一部みたいな感覚でしたね。例えば、僕は創業支援や特産品振興の部署にいたこともあり、NPO活動で出会った人とそのまま行政の仕事につながることも多かったんです。
タカラトミー社を通じて音楽配信会社の方と出会い、最終的には市とその企業で創業支援の協定を結ぶことになったこともあります。結果として、NPO活動が本業のネットワークにもなっていきました」(田中さん)
当初は「変わった公務員」だと見られることもあったといいます。しかし次第に「話を聞いてみたい」と関心を持ってくれる人が増えていったそうです。

「最初は『なんか変な公務員だな』と思われてたと思います。でも、名刺を渡すと『こんなこともやってるんですね』と興味を持ってもらえて、話を聞いてもらえる。結果として、普段は接点のない人たちとつながることができる。市の職員としてそういうネットワークを築けるのは、すごくありがたいことでした」(田中さん)
田中さんにとって、NPO活動は市職員という“本業”から離れたもう一つの顔ではなく、むしろ地域との接点をより深くするための“もう一つの入口”だったのかもしれません。
「まちが変わる」は人が動き出すことで始まる
『まちあそび人生ゲーム』の活動が全国各地へと少しずつ広がるなかで、田中さんは“イベントの成果”について何度も問われてきました。
「地域がどう変わったのか」「経済的な効果はあったのか」——そうした問いに対して、田中さんが返すのは、楽観でも悲観でもなく、10年続けてきたからこそ語れる率直で現実を見つめた言葉でした。

「正直、イベントをやったからといって劇的に商店街が変わったとは、あまり大きな声では言えないんです。
そんなにうまくいく話だったら、みんな全国でとっくにやっていると思うし、本当にまちが変わるなら、行政ももっと積極的にやると思います。
だから目に見える成果という意味では、そこまで大きな変化はないのかもしれません」(田中さん)
それでも、田中さんが活動を続けているのは、別の“変化”に価値を見出しているからです。それは地域そのものではなく、そこに関わる“人の変化”でした。
「イベントを通して、『ちょっとやってみようかな』と思う人が出てくるんですよ。今まで関心がなかった人が『手伝いたい』と言ってくれたり、自分のお店のアイデアを出してくれたり。そういう人の変化こそが、数字では計測はできないけれど、本当の成果なんじゃないかと思います」(田中さん)
どんなに仕組みが整っていたとしても、「まちを変えたい」という誰かの想いが育たないことには、地域の変化ははじまりません。

田中さんたちは、『まちあそび人生ゲーム』の企画の枠組みや仕掛けを整える一方で、「イベントの“中身”をつくるのは、あくまで地域の人たち自身」というスタンスを貫いてきました。
「実施は想像以上に大変ですよ」と伝えたうえで、それでもやろうとする地域の覚悟と熱意を信じて任せる。だからこそ、その過程で芽生える“自分ごと”としての関わりが、人の変化を生んでいるのかもしれません。
“変える”ということは、自分らしい関わり方を選ぶこと
2024年、田中さんにとって節目となる出来事がありました。
それは、全国の自治体職員が集まる研修所(滋賀県)で講師を務めたこと。地方公務員としての自身の歩みを振り返りながら、90分の講義を担当しました。
「研修のオファーがきたときに、“集大成に近いな”と感じました。10年間やってきたことを、次につなげる場が来たのかもしれないと」(田中さん)
講義のテーマは「イベントと地域振興」。『まちあそび人生ゲーム』を中心とした活動を紹介しながらも田中さんが伝えたかったのは、“面白いことを仕事の枠を越えて実践していいんだ”という姿勢でした。

「公務員とNPOという立場を両立する“2足のわらじ”のあり方について、ひとつの形を示せたのではないかと思っています。例えば、出雲市役所には約1,500人の市職員がいます。その中に、1人や2人、ちょっと変なことをやる人がいてもいい。そんなふうに若い職員が思ってくれたらうれしいですね」(田中さん)
実際、出雲市内でも朝市を開いたり、エクササイズの講師をしたり、“越境”職員が少しずつ増えているといいます。
『まちあそび人生ゲーム』を通じてまちを変えようとした10年は、いつしか「誰かの背中を押す10年」へと形を変えていました。
「見方を変えれば、『まちあそび人生ゲーム』もひとつの地域活性のツールにすぎません。それ自体で何か劇的に変わるというよりも、『こういう関わり方もありなんだ』と気づくキッカケになればと思います」(田中さん)
小さな実践が、少しずつ自治体の中に種がまかれていく。その営みこそが、“ローカルを変える力”の正体なのかもしれません。
Information
2025年「WHERE ACADEMY」体験会を開催!
「自信のあるスキルがなく、一歩踏み出しにくい…」
「ローカルで活躍するためには、まず経験を積まなくては…」
そんな思いを抱え、踏みとどまってしまう方に向けて、
地域活性に特化したキャリア開発アカデミーをご用意しました!
「インタビューライター養成講座」「地域バイヤープログラム」「観光経営人材養成講座」など、各種講座でアナタらしい働き方への一歩を踏み出しませんか?
<こんな人にオススメ!>
・都心部の大手・ベンチャー企業で働いているけど、地域活性に関わりたい、仕事にしたい
・関わっている地域プロジェクトを事業化して、積極的に広げていきたい
・地域おこし協力隊として、活動を推進するスキルや経験を身に着けたい
まずは体験会へ!
参加申し込みはこちら
Editor's Note
編集後記
なぜ毎日歯磨きできているのだろう、と考えてみる。毎日欠かさずに続けるために、必要なことは良い意味で「頑張らないこと」なのかもしれない。何かを「始めること」「続けること」、ちょうどいい力の塩梅でやっていきたい。

ASAHI KAMOSHIDA
鴨志田あさひ
Articles
