LOCAL LETTER


今までのやり方では通用しない?移住者が語る地域との関わり方
KYUSHU
九州
拝啓、地域に入り込んでいきたいけど、どうしたらいいかわからないと悩むアナタへ
※本レポートは、『ONE KYUSHUサミット』のSession4「地域の可能性を見つけ、育て、広げる共創の力」を記事にしています。
アナタに伝えたい地域の魅力はありますか。
豊かな自然、あたたかい人びと、まちを彩る個性的なお店たち。
地域の魅力は、地元の人にとっては当たり前すぎて、見えにくいことがあります。
外からの視点や移住者のまなざし、さらには国際的なつながり。そういった外部のフィルターを通し、言葉やプロダクトとして形を変えることで、初めて地域内外に価値として伝わっていきます。
本セッションでは、移住を通じてその土地で活躍する方々が登壇。モデレーターの日野さんのリードのもと、自由で多角的な議論を通じて、地域とどう関わり、可能性をどう見つけ、育て、広げていくのかを探ります。
地方、台湾、東京、生まれや住まいがバラバラな自分たちの、それぞれの地域との関わり方
日野氏(モデレーター、以下敬称略):お話いただくにあたり、参加者への解像度を上げていけたらと思います。ご自身の活動と、自己紹介をお願いします。
池田氏(以下敬称略):パーソルキャリアの「HiPro Direct(ハイプロダイレクト)」で、地域アンバサダーを務めています。「HiPro Direct」とは、地域の事業課題を抱えている事業者と、主に首都圏の専門人材をマッチングするサービスです。 僕はプロの人材と事業者をつなぎ、ビジネスを推進していくハブとしての役割を担っています。

門田氏(以下敬称略):五島つばき蒸溜所の門田です。
キリンビールで28年働いていましたが、世界に誇れるクラフトジンを作ろうと、キリンビールの仲間3人と縁もゆかりもない五島へ来ました。今年の12月で開業して丸3年になります。その後、五島や上五島出身の方に入社いただいたり、キリン出身のメンバーにもジョインしてもらったりで、現在は6人で世界に誇れるジンを作ろうと、一生懸命頑張っています。

蔡氏(以下敬称略):蔡 奕屏(ツァイ イーピン)です。出身は台湾です。2017年に千葉大学へ留学しました。これまで日本のローカルに関する書籍「地方設計」と「地方編集」を台湾で出版しています。
中国語の地方という言葉には田舎という意味合いはなく、ただ「ローカル」という意味。そのため私のしている仕事はいつも「ローカルデザイン」だと説明しています。本の出版前後はライターとして日本の地域を取材したり、発信したりしていました。出版後は日本と台湾がもっと交流できるようなプロジェクトを行っています。
「もっと現地の方々に会いに行きたい」「現地のフィールドに視察に行きたい」というリクエストが増えてきたので、台湾の政府関係者や大学教授、企業の方をアテンドし、日本のローカルを回っています。今私は福岡在住なので、視察先は九州がかなり多いです。
台湾人が日本に足を運ぶという一方方向の交流ではなく、もっと双方向で、台湾のことを日本の方に紹介したいと思っています。
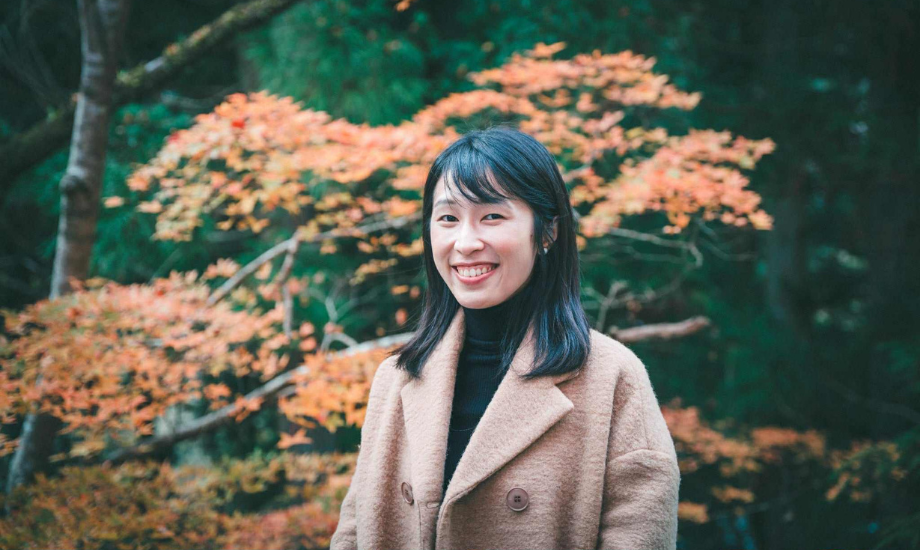
日野:僕も自己紹介をさせてください。博報堂ケトルという広告会社で働いています。出身は福岡県福岡市です。東京の広告会社にいますが、地域を盛り上げる企画に携わることが多いため、会社ではローカルおじさんと言われています。
また、5年前に立ち上げた「Qualities」というウェブメディアの編集長もしています。
「Qualities」の 「Q」は九州の“キュー”ということで、取材テリトリーは九州です。 九州のいいことを探しに行くぞ、という思いで運営しています。
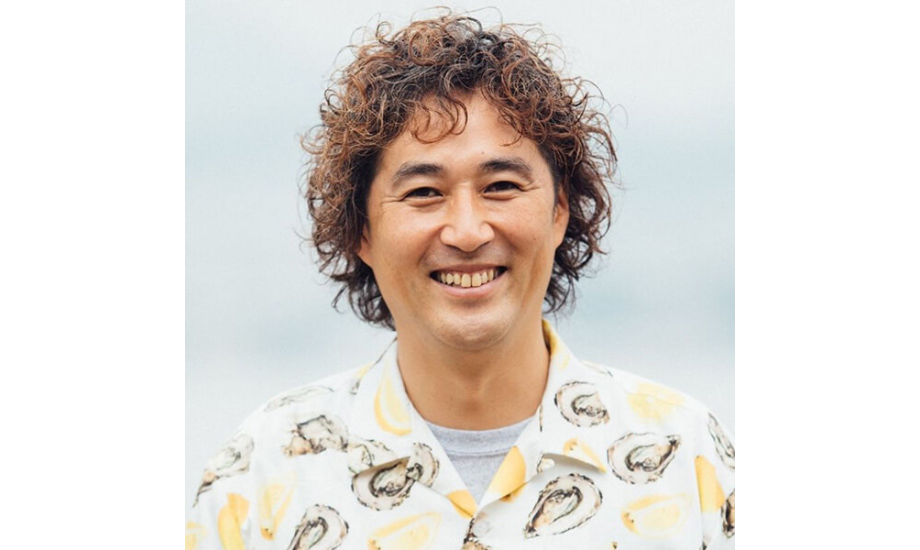
日野:先月には「一般社団法人バイローカル」を立ち上げました。「バイローカル」を簡単に直訳すると「近所のものを買いましょう」ということです。
「自分の住んでいるエリアの良き商い」を大切に、いい商売、いい生産をしている人たちのことをもっと知り、その人たちの商品を買ったり、そのお店に足を運んだりして、お互いに応援し合う。そんな日常を作れるまちの方がみんな幸せになる、という考えのもと立ち上げました。
便利だからと大手ECサイトなどで購入を続けていたら、地域のお金がどんどん外に流れてしまいます。頑張っている地域の人たちから買い物をすることによって、お金を地域の中で回していく。全員が幸せを感じながら関われたら、と思って取り組んでいます。
今までの「東京中心」のビジネスモデルは長く続かない。地域との関わりから知る、これからの道筋
日野:池田さんは会社を退職されたと伺いました。
池田:8月末にパーソルキャリアを退職し、10月からは業務委託として契約を結んでいます。現在は八丈島に住んでいます。
パーソルキャリアで働いていた時、副業で週末に招待制のバーをしていました。そこで扱っていたレモンリキュールに八丈島のレモンが使われていて、その収穫を手伝いに行ったのが八丈島との 出会いです。その後、1年4ヶ月という短い期間で移住まで至っています。
初めて泊まったゲストハウスの女将さんと意気投合したのですが、その方が島の名士の娘でした。当時HiPro Directで地域の事業者の開拓を進めていたので、八丈島の事業者は女将さんから紹介してもらいました。観光ではなく、「仕事」という角度からこの地域のコミュニティに入れたというのが、地域に溶け込むうえでやはり大きかったです。

日野:最近大企業も、これまでのような事業展開ではもう難しいと分かり始めていると思います。例えばデベロッパーによるまちの開発。昔は年々人口が増えていたので、新しい魅力的な場所を作ればそこに人が来て、そこを借りたい人がたくさんいた。テナント収入で儲かるというビジネスモデルが成り立っていました。
しかし、人口も減少していく中で、もうそのモデルが成り立たなくなっていると感じ始めています。大企業として、大勢の人を便利にするためにしていた事業が、実は地方からお金を吸い上げてしまっていると感じつつも、その流れを止められずにいる。
企業もその地域に関わり、向き合っていく必要があると気づいていはいると思うんです。地域の人たちとどう交わっていいかがわからず、接点を作るのがまだ上手にできずにいると僕は感じています。
日野:池田さんはパーソルキャリアという大企業で、システマティックに1人でも多くの人材をマッチングさせた方が勝ちという価値観を大きく転換して、36歳で仕事を辞めて地域に向き合う生き方を選びました。
池田:大手企業が地域に入ろうとすると、マネタイズの側面だけでなく、地域の方とつながっていくことすら難しいと感じることがあると思います。難しいながらもコミュニティに密に入ることで、僕の生き方のテーマは「心の豊かさ」に大きく変わりました。これが移住するに至った理由です。今焼酎蔵を手伝っていますが、自分はこの地域やコミュニティに対して何ができるのか、悩みもがきながらも模索している段階です。
地域から受け入れられる方法は、その土地のものを大切にすること
日野:大企業の理論でマーケティングや面白い企画を立てたとて、地方では上手くいかないという話もあります。
ですが、門田さんのジンは島の皆さんにとても応援をされて、飲んでもらえるようになっています。準備期間も含めた4年間でそこまで至っているのは、皆さんの人柄や、地域への向き合いをとても丁寧に行なってきたからだと想像できます。
門田:最初は警戒されたのも事実です。当初、キリンから来て、すごい工場ができて、ジンとかいうよくわからない酒を作るらしい、と尾ひれがたくさんついた噂が流れていました。来てもらえればわかりますが、本当は小さな工場なのですが。
五島つばき蒸溜所は半泊(はんどまり)という、福江島の中でも北東部の少し離れた場所にあります。4世帯5人しか住んでいない集落です。そこの小さな教会には神父さんが1人しかいないので、僕たちで教会の維持管理も一緒にさせていただきたいと思っていました。
その話をしたら「現在教会を管理している浦頭(うらがしら)教会の三役に説明をしてほしい」と言われて。話に行ったら、僕1人に対して、相手は20人だったんです。

日野:20人も!それはすごいですね。
門田:最初は質問内容も厳しかったです。島の人は工場など不要だと思っているので、基本は歓迎されません。
ですが、ある人が「原料は何を使うんだ?」と聞いてくれました。その時に「椿を使いたいと思っています」と答えたんです。
蒸留所がある奥浦という北部のエリアには、椿油の製造所があります。椿油は江戸時代からの高級品です。今でも高値で取引されていて、島のおばあちゃんには10万円、20万円と稼ぐ人もいます。それぐらい、椿を育てるという文化が根づいていて、椿の採集をする人もたくさんいます。
なので「俺が集めた種を酒に使うの?」と言ってくれて。自分たちで集めた種がお酒になる、ととても喜んでくれました。
しかもその次に「アルコール度数は何度?」と聞かれて「47度です」と答えたら一気に場がざわつきました。お酒好きが多いので、アルコール度数が高いほうが良いんです。ここから一気に空気が変わって、打ち解けられました。
日野:原材料として拾い集めて出荷していただけの椿が、自分たちの大好きなお酒に変わっていくという点が、非常にうまく噛み合ったんでしょうね。
門田:ジンに利用する椿は最初は購入し、その後は自家栽培した方が消費者へのストーリーとしては伝わりやすいのではないかと思っていました。
だけど、まちの人びとの反応を見たら考えが変わりました。島の皆さんが集めている種で作っているって、最高じゃないですか。ですので、自分たちで自家栽培したものを使うのは絶対にやめようと思いました。
今は定期会員で買ってくれる方が1200人ぐらい。そのうち島内の人は20人ぐらいです。元々、月800本ぐらい生産しようと計画して立ち上げましたが、今は5000本ぐらいの予定です。

日野:僕が「クオリティーズ」で取材する方々も、まずは地元に何もないと思って出ていき、県外で何かを頑張ってくる。そうして追い詰められた時に地元を見つめ直したら「うちの地元にはあれがあるじゃないか」と思い出す。
九州に帰ってきて実感した地域の価値を大切に編集したり、頑張ってプロデュースしたりした人たちが、現場で変化を起こしているというパターンが結構あります。
門田:立ち上げから販売が追いつかなくなった理由の一つとして、長崎や五島に根付く贈答文化もあります。最初は地元の方が贈答用として使ってくれたことで、ブームに火がついたんです。今もその流れは続いていますね。
日野:教会の管理に関しても、きっと五島の中ではとても大事にしてきたことですよね。でも担い手不足で頭を抱えていたところに、門田さんたちがやってきた。掃除だけではなくて、多分地元の方々にとっては管理してもらう意味合いが大きいんでしょう。
門田:教会の管理も楽しいです。
日野:お話されている顔を見ていたら、それが伝わってきます。
Editor's Note
編集後記
自分たちの”当たり前”が、自分たちの大好きなものになる。これは外からの視点がなければできなかった共創のエピソード。もしかしたら、あなたの地域に当たり前にある“それ”も、あなたの大好きなものに化ける可能性もあるかもしれません。

Natsuki Mukai
向 夏紀
Articles
