LOCAL LETTER


自走と伴走の両輪が「10倍速」の成長に。独立を目指して挑戦する仲間を募集
ZENKOKU
全国
地域課題に挑戦したい想いと、起業への不安。その間で揺れるアナタへ
地域に根づいて、課題解決に挑戦したい。
起業も考えるけれど、経営なんてしたことがないし……。
伴走してくれる人がいたら。でも、キャリアは自分の意思で積みたい。
確かな想いと不安の狭間で、一歩が踏み出せない人もいるのではないでしょうか?
そんな課題に応えるべく、地域で挑戦する人が「リスクを持たなくてもいい仕組みづくり」と、「圧倒的に成長できる環境づくり」に取り組んでいるのが、株式会社ビッグゲート(以下、ビッグゲート)です。
IT技術を駆使して地域課題の解決に挑むビッグゲート。ふるさと納税事業や地域商社の設立なども手掛けています。同社の大きな特徴は、事業や地域商社を立ち上げてから数年で、現地法人として分社化していく事業展開です。
現在ビッグゲートでは、分社化を見据えて地域の「中核を担う人材」を募集しています。
本記事では、独立への想いを胸にビッグゲートで新たなキャリアをスタートしたお二人にお話を伺いました。ビッグゲートが大切にする地域での事業の在り方や組織のカルチャー、根底にある価値観に迫ります。
求む。地域の未来を託し、独立を志す挑戦者
同社が今、特に仲間を求めているポジションが2つ。宮城県石巻市にあるふるさと納税事業所の責任者と、大分県玖珠町などに置く地域商社事業のプロジェクトマネージャーです。
「石巻で求めているのは、僕の後任として、石巻市ふるさと納税事業の責任者を務めてくれる方です。予算配分や人材配置の裁量を持ちながら、5名程度のチームを率います。
事業計画の立案や実行、自治体・地域事業者との連携などを進め、現在の年間寄付額約20億円を今後4年間で40億円規模へ成長させることを目指します」(中村さん)

地域商社事業では、地域に移住して、ふるさと納税事業の立ち上げやプロジェクトマネジメントを担います。自社開発のシステムを活用しながら、道の駅の運営や商品開発、地域イベントの開催も行っています。
「現場マネージャーとして自治体・生産者・事業者とコミュニケーションを取りながら、地域を盛り上げます。候補地は複数あり、僕がいる大分県玖珠(くす)町もそのひとつです。地域商社の設立を見据え、2027年に現地法人の立ち上げを目指しているため、開業準備から一緒に挑戦してくれる仲間を募集中です」(石黒さん)

ビッグゲートの事業所や地域商社の責任者は、まずは、ふるさと納税をはじめとする各事業の運営の方法やビジネスの仕組みを学びます。そして事業として自走できるようになれば、地域の現地法人として独立して運営していくことになります。
こうして、立ち上げ期は会社が責任を持って運営を支え、挑戦する人はリスクを一手に背負わずに事業経験を積むことができます。独立の際には、ノウハウとネットワークを持った状態でスタートできる——これが、ビッグゲートが掲げる「リスクを持たなくてもいい仕組みづくり」です。
実際に北海道鹿部町では、2018年に「株式会社シカベンチャー」が設立され、道の駅の運営や地域資源を生かした事業をビッグゲートから引き継いで展開しています。地域と共に歩む姿は、ビッグゲートのモデルケースとなっています。

通常であれば事業を自社に残して、利益を確保するはず。そうではなく、あえて独立させる。その決断には、ビッグゲートならではの考え方が表れています。
「たとえば地域商社を育てたあと、利益のためにそのまま自社で囲い込む形もあると思うんです。でも、当社の考え方は違っていて。
最初は地域の中間事業者としてビッグゲートが運営し、3年ほどしたら現地法人として分社化する。地域商社が自走できそうな状態になったら、『地域の中でどんどん動かしていって』と。
『さよなら』ではなく、『頑張って』と切り離します。そうして、その地域の資本にしていくのです」(中村さん)

分社化して「地域の会社」にすることで、地域外から入ってきたお金も、地域内で回るようになる。得られた収益もまちに再投資しやすくなる。
地域に根ざして、課題解決の循環を加速させる。それが、「ビッグゲート流」の事業展開です。
「事業展開を実現するためにも立ち上げ時から担当者を地域に置き、人とのつながりを大切に育んでいます。自治体や地域の方々との距離が近く、密接に関われていることが、事業としての強みにもなっています」(石黒さん)
アスリートからローカルの担い手へ。二人が歩みはじめた新たなキャリア
中村さんと石黒さんも独立や起業への想いを胸に、ビッグゲートで新たなキャリアを歩みはじめました。
アスリート人材を積極的に採用するビッグゲート。PDCAサイクルを回し続ける姿勢や正解のない問いに試行錯誤しながら行動する力が、地域の未来をつくる人材に必要な要素だと考えています。

大学卒業後からフットサル選手として活動していた石黒さん。セカンドキャリアとして玖珠町の企業誘致の活動に取り組んでいたときに、ビッグゲートと出会い、入社を決めたそうです。
「自分の経験も踏まえて、スポーツ選手のセカンドキャリアを後押ししていけるような会社をつくりたいという思いがずっとありました。だから、自分が関わった元アスリートの方を導けるような会社もつくっていきたいんです。
人材育成も、ゆくゆくは担えたらと考えています。玖珠町で経験を積んで、ほかの自治体とも関係性ができてきたら次の地域に移っていくようなイメージで、キャリアを重ねていけたら嬉しいですね」(石黒さん)

同じく中村さんも、アスリート引退後に起業を目指してビッグゲートに入社しました。
「僕の祖父が起業家ということもあり、ずっと続けてきたスピードスケートを引退するときに次の目標として浮かんだのが『起業』でした。地域に目を向けると、人の流れが減っていることに課題を感じています。若い人たちの地域流入を増やしたいという思いもあるんです」(中村さん)
3倍、10倍の成長を実感。挑戦が人を育てる
そんなお二人がビッグゲートへの入社を決めた理由には「成長できる環境」があるといいます。

「やる気次第では3倍どころか、10倍のスピードで成長できる環境」と経験から語ってくれたのは、中村さんです。
「各事業所の責任者にある程度の裁量権があるため、『成果を出すなら、自由にやっていいよ』と言われます。高い自由度が当社の強みかなと思っています」(中村さん)
中村さんは入社からわずか3ヶ月で、石巻事業所の責任者になりました。就任直後にふるさと納税の運営に関わるルールが変更され、石巻市にある約170の事業者へ説明会を開くことになりました。

「当時はふるさと納税のルールをまだ何も理解できていない中で、すべて自分が説明しなければならない状況でした。それを乗り越えられたのが、今となってはよかったなと。
いろいろミスもありました。でも、会社の懐の深さというか、ミスを責められるわけでもなく、とにかく実行して改善、改善、改善・・・という感じで。
実際にできているかというと自己評価にはなりますが、勉強環境や成長環境を与えてもらってきました。3倍、4倍、5倍、10倍の成長環境があると考えています」(中村さん)
大きな裁量とサポート。成長を支える、絶妙なバランス
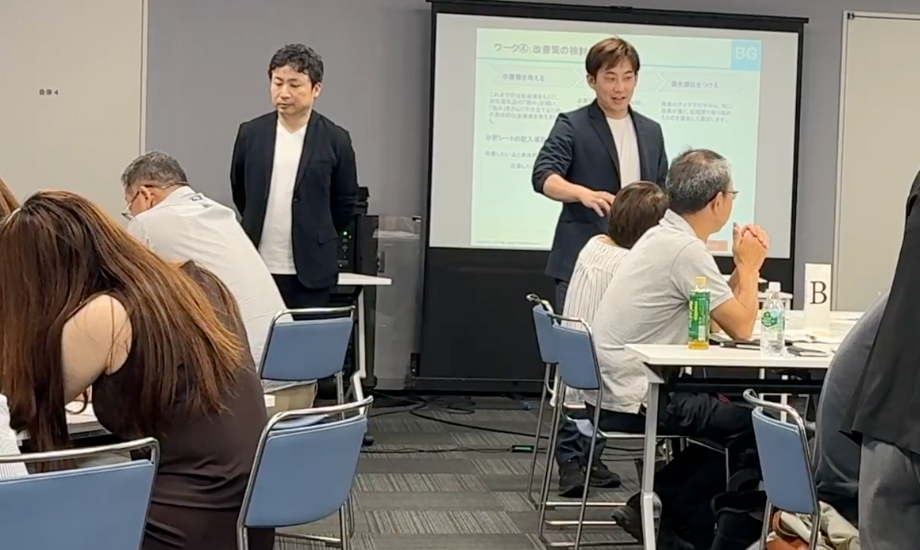
「3倍、10倍増しの経験ができる環境」を支える土台の1つが、仲間同士で助け合う文化です。ミスが起きたときに個人を責めないこと。同社の鉄壁のルールだといいます。
「仕事なので、いいことも悪いこともある。悪いことが起きたとしても、みんなで助け合う。わざわざ言わなくても、それが『当たり前』という文化があります」と話すのは石黒さんです。
「ちょうどいいバランスで手を差し伸べてくれて、すべて答えを与えるのではなく、自分で考える部分をしっかりと残して接してくれる。『成長できる会社』という表現は、当社を表す言葉としてとても適していると思います。
言葉を選ばずに言うと、『頑張るしかない環境』をつくるのがとても上手な人が多いなと。頑張るというと抽象的ですが、追い求めてやれる資質がある人が集まっているのかなと思います」(石黒さん)

仕事で困難に直面しても、考え方の筋道や次に相談すべき人を示してくれる。
挑戦し、壁を乗り越えるために身につけるべき思考プロセスについて、さまざまな立場や視点から助言をもらえる環境。二人は、そのアドバイスを「的確な詰め」と表現します。

事業の責任者は、代表の大関さんと対面では月に一回、リモートでは週に一回ほどの頻度で、面談や打ち合わせの機会があるそう。
「感情的ではなく、ロジカルな答えを求められます。不足している視点を、改善するまで根気強く、ずっと問い続けてくれる。『おんぶに抱っこ』のような状態はよくないと思いますが、成長するまで育ててくれる環境があります」(中村さん)
「成長したいと思えば、周りの人たちがその環境を与えてくれます。もちろん、与えられているからこそ、結果へのプレッシャーもありますが。裁量と責任のバランスが絶妙だなと感じています」(石黒さん)

成長を求め、地域に挑む人へ
圧倒的な成長環境とそれを支える企業文化。ビッグゲートは、どんな人にとって最適な場と言えるのでしょうか。
「明るく素直で、前向きで、成長への意欲がある人です。その素養があれば、学びながら成長していけます。
もちろん必要なスキルをすでに持っているなら、より歓迎です。でも入り口としては、スキルより人柄。地域の人たちとも関係性を築いていくので、人間性が一番大切だと思っています」(石黒さん)
「本来、起業は不安を伴うことです。その点ビッグゲートでは、成長環境があってチャレンジングなこともできつつ、会社の中で安定してじっくり考えることもできる。起業したい、いろいろ挑戦したいという人にとって、とてもいい環境ではないでしょうか。
人生は楽しんだもの勝ちだと思っているので『自分を試したい』という人に、ぜひ仲間になってほしいですね」(中村さん)

経験から責任者として課題や挑戦に取り組み、無我夢中で壁を乗り越える日々。
それでも、入社してからの歩みを語る二人の表情は、とても晴れやかです。
挑戦できる環境は、整っています。
さあ、アナタの一歩をお待ちしています。
採用情報の詳細はこちらから
Editor's Note
編集後記
ベンチャーだけれど、そう感じない一面も。絶妙で巧妙なバランスが印象的でした。仲間が増え、最近では理念の浸透へ、社内発信をはじめたりもしているそうです。地域と、会社とともに成長する。そんな環境での挑戦。ワクワクの連続が待っているのではないでしょうか。

Mayumi Yanai
柳井 麻友美
Articles
