LOCAL LETTER


アカデミアとのコラボレーションが地域課題解決にもたらすものとは
JAPAN
全国
拝啓、都市のアカデミアが地域課題解決にどのような影響を与えているか知りたいアナタへ
※本レポートは、三井不動産株式会社、NewsPicks Re:gion主催のイベント「これからの地域経済をつくるための祭典『POTLUCK FES’23 -Autumn-』」にて行われたセッション、「アカデミアは地⽅の未来に何を実装できるのか」を記事にしています。
アカデミア、すなわち大学における研究者と聞くと権威があり、一般人からすれば大きな隔たりを感じるようにも思われます。しかし、彼らの研究が様々な地域の発展に関連していることは、確かな事実です。
本記事では、地方においてアカデミアの協力によってどのように技術革新が取り入れられ、多くの地域課題を解決してきたかを登壇者らが語りました。
地域の課題に丁寧に向き合い、スローデジタルで解決する
西村勇哉氏(モデレーター、以下敬称略):本日は、越塚先生のこれまでの取り組みや問題意識をもとに、どのようにに社会の役に立ちたいと思われているのか、またどういう役割分担をするといいコラボレーションができるのかというところから、地方の未来への価値を見つけていきたいと思っています。まずは自己紹介をお願いします。
越塚登氏(以下敬称略):東京大学の情報学環におります。専門は地域活性とは全く縁がないコンピューター関連ですが、以前から地域と関わった活動をしています。
これまでに、高知県、千葉県市原市、神奈川県横須賀市・小田原市、山口県宇部市、熊本県熊本市・山江村などのプロジェクトに関わりました。この他に連携協定を結ばずに取り組んでいる地域もあります。
このうち高知県とは2018年に協定を結び、2019年には高知の農業にAIを導入しました。20代から関わっているのでもう30年以上のお付き合いになります。
茄子は高知県の生産物の中心的な商品で、温室栽培ができます。大都市のマーケットからは遠く、面積は広いのに平地がほとんどない、そんな農業には不向きな高知での栽培についてJAに相談したところ「ポイントは生産量を増やすことではなく、出荷時期のコントロールだ」と言われました。温室で環境を制御して、周辺の近郊農業地域が作らない時期に出荷する必要があるのです。
生産した茄子は、なるべく高く買ってくれる大手スーパーへ出荷したいところですが、大手スーパーの買取条件は毎日1万個です。「天候不良なので5,000個しか出せません」ではだめで、平均して毎日1万個生産しないといけない。それには出荷時期のコントロールが必須ですが、熟練した農家でないとできないことでした。
ではそれをAIができたらいいのでは?ということで、農業未経験者にデータを渡して収穫の予測をしたところ、茄子作りの名人の農家さんとほぼ同じレベルまで予測ができるようになりました。それを高知県中の温室で行い、AIのデータの蓄積を県全体で集めて、データのプラットフォーム「SAWACHI(サワチ)」を作りました。

越塚:高知はカツオをはじめとした漁業が盛んなため、「NABRAS(なぶらす)」という漁師向けのデータ提供も県と一緒にやっています。海の向こうに直径5mほどのブイを置き、そのブイに山のようなセンサーをつけて、衛星通信でカツオの漁獲量を予測する。それをデータ基盤にして漁師さんのスマートフォンに送ります。
また中部電力とのコラボで、スマートメーターが自動でフレイルの検知をする仕組みも作りました。フレイルとは要介護になる一歩手前の状態のことで、従来は半年や1年に1回のアンケートで調べていましたが、それだと手遅れになる可能性がある。電力メーターを見ることで家の様子がわかるので、スマートメーターの電力量の消費データを解析することで自動的にフレイルを検知できないだろうか?ということで始まりました。
従来、電力メーターは検針以外の用途が認められていませんでしたが、法改正されたことでフレイル検知に使用できるようになったんです。今では中部電力による「eフレイルナビ」という行政向けのサービスの運用が始まっています。
同じく電力メーターを使用した地域課題解決で言うと、横須賀市のケースがあります。佐川急便と提携して、不在時には配達せず在宅時に届けるしくみを作りました。横須賀も平野が少なく、崖が切り立つ地形です。宅配業者にとって再配達が厳しい地形のため、在宅か不在かを検知して不在配達を少なくすることが地域課題の解決となり、評判になってメディアにも取り上げられました。メディアに取り上げられることによって連携の動きも促進するので、僕らも地方自治体も活用しながら一緒にやっています。
僕の合言葉は「日本のGDPに1円も貢献しないIT」。いわゆるスローデジタル、のんびりするためにITを積極的に使っています。東京大学は地域課題に興味が無いのではと思われるかもしれませんが、実は東京出身の学生はあまりおらず全国から来ているので、地域課題に興味を持つ学生は多いです。地域に携わると今まで全く気がつかなかったことを知ることができますし、それがとても楽しいんです。
アカデミアの専門性が、地域課題解決に生かされる可能性はどのくらいか
西村:先程のフレイルやカツオの話は、最終的なアウトプットを見ると、素晴らしい結果が出ていると思います。プロジェクトのどの部分でご自分の強みが出て、生きたなと感じるのでしょうか。結果が出るまでは、わからないものなのでしょうか。
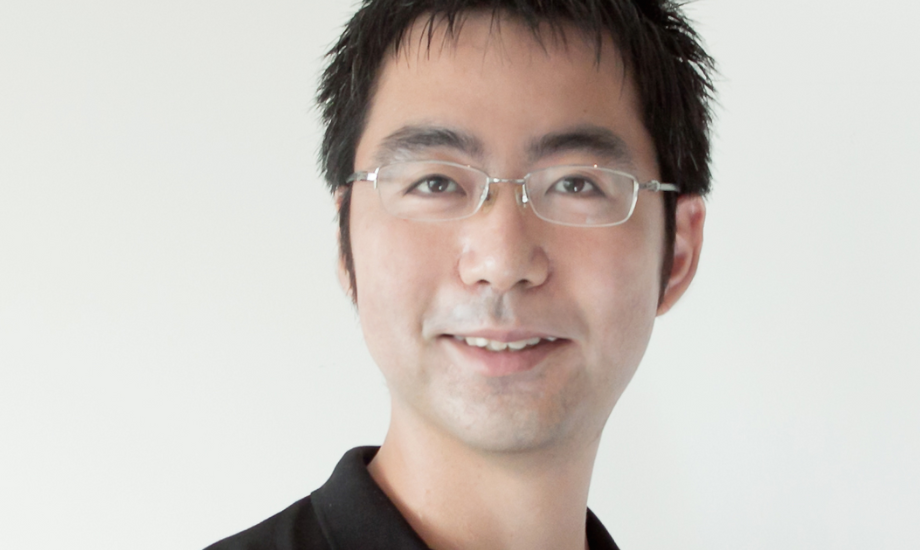
越塚:専門を生かすことについて、自分で考えたことはあまりないですね。夜一緒に飲んでいて盛り上がった時に出た話に取り組むとか、そんな偶然の連続が普通にあります。長い時間をかけて信頼を築いて、10年くらい一緒にやっていると、その先生の専門が生きることが1回くらいあるかもしれません。
失敗することも当然あります。例えば、スターリンク (Starlink) を農業現場に置いて使っており、100Mbps出るのでカメラの映像を東京に送って画像認識をしていました。これをカツオ漁船に乗せたかったのですが、違法とわかり中止することになりました。海上と陸上とでは技適(電波法令で定めている技術基準)が違うので、陸の装備を海でそのまま使うと違法になってしまうんですね。
西村:僕らからするとデータが出てきた後に連結したり、予測までしてくれるというのは本当にすごいことです。それは農家だけでも、技術者だけでもできない。いい材料が出てきたら専門性が生かせることもあるのではと思いましたが、その点はどうでしょうか。
越塚:むしろいい材料が出た時こそ自分たちだけでなく、同じことを研究している地域の大学と分担して行う方がうまくいきますね。
都市と地域のアカデミアのタッグが、地域の課題解決を促進する
西村:アカデミアには2種類あって、1つは都市部を拠点とした情報の交差点的な役割で、スタートアップ経験者も比較的多くいるところ。もう一方は、地方に根付いて技術を生かすところです。
地方の国公立大学と地域が組んで、プロジェクトをする道はありますが、それだけだとうまく行かない部分があるかもしれません。そこに都市部にある東京大学が加わり、地域との三者で連携する意義はどういったところにあるのでしょうか。
越塚:学術的な知見の交換よりも必要なことがあって、それが東京で繰り広げられているコラボレーション的な動きです。そういった動きが地方にはない。連携することで、その空気感を伝えたいんです。
実際、僕の研究室内だけでも約半分の学生がベンチャーをやっています。これが地方へ行くと、地域の大学全体でベンチャーが数個しかないという状態です。地方だとベンチャーの興し方を先生がわからない。その雰囲気的な部分を伝えたいですね。学術的なことは東京でも地方でもそんなに変わらなくて、それをビジネス化するときの一連の動きについての格差は感じています。

西村:東京大学は、大学のスタートアップが日本で一番多いですが、越塚先生の周りでもそんな先生や学生はいらっしゃいますか。
越塚:たくさんいます。学生がベンチャーをやって上場して億万長者になったら、他の学生はそっちのいうことを信じるよね。教育がすごくやりづらい(笑)
西村:ベンチャーを興すことは、そんなに当たり前のことなのでしょうか。
越塚:はい。でもそれは僕らの学生時代もそうでした。当時はバブルで任天堂が出てきたころで、周りもベンチャーだらけでした。今またその周期が来ていて、若い人が活躍できている。産業的にも新しいITへの移行期かなと思っています。
東京に本社がある会社で、ワールドワイドな会社は実はそんなに多くありません。例としてトヨタの本社は東京ですが、技術の本体は名古屋です。地方には起業の素地があるけど、東京には意外とない。そして地方から出てきてワールドワイドになる会社は地元の大学をとても大事にしていて、産学のタッグを組んでいます。

西村:地域の大学とコラボレーションする際は、どのような感覚で臨んでいますか。
越塚:僕は「来るもの拒まず、去る者は追う」主義です。要は欲張りなだけで、茄子もフレイルも全然知らない話でしたが、これまでの経験上、相手から来る話はいい結果になることが多い。自分に話が来るには何か理由があって、それに応えることにも意味があると思っています。そうやって何年かすると、世の中が自分の受けた案件の方に動いています。
でも僕らは地方に行ったら絶対よそ者なので、分をわきまえないといけない。地域の大学とコラボレーションして、最終的には自分たちの知見も何もかも全てその地域に移管する覚悟は持っています。
西村:都市部と地方のアカデミアをひとくくりにせずクロスさせると、今までにないタッグが生まれる。両者で組んで地方に入ることができると強いですね。
前編記事では、アカデミアの協力によって地方にどのように技術革新が取り入れられ、多くの地域課題を解決してきたかをお届けしました。後編記事では、実際に地域課題解決の協力をアカデミアに依頼するにあたって直面する疑問や、アカデミアとしての地域課題への向き合い方についてお話しいただきます。
Editor's Note
編集後記
地域とアカデミアが組むプロジェクトは多々存在するが、組む側の気持ちというものについて、一般人はあまり考えることはないように思います。異なるベースを持つものが合わさる時の率直な心境に触れることで、身の回りのプロジェクトにも関心を寄せる機会が増える気がしました。

KAYOKO KAWASE
河瀬 佳代子
Articles
